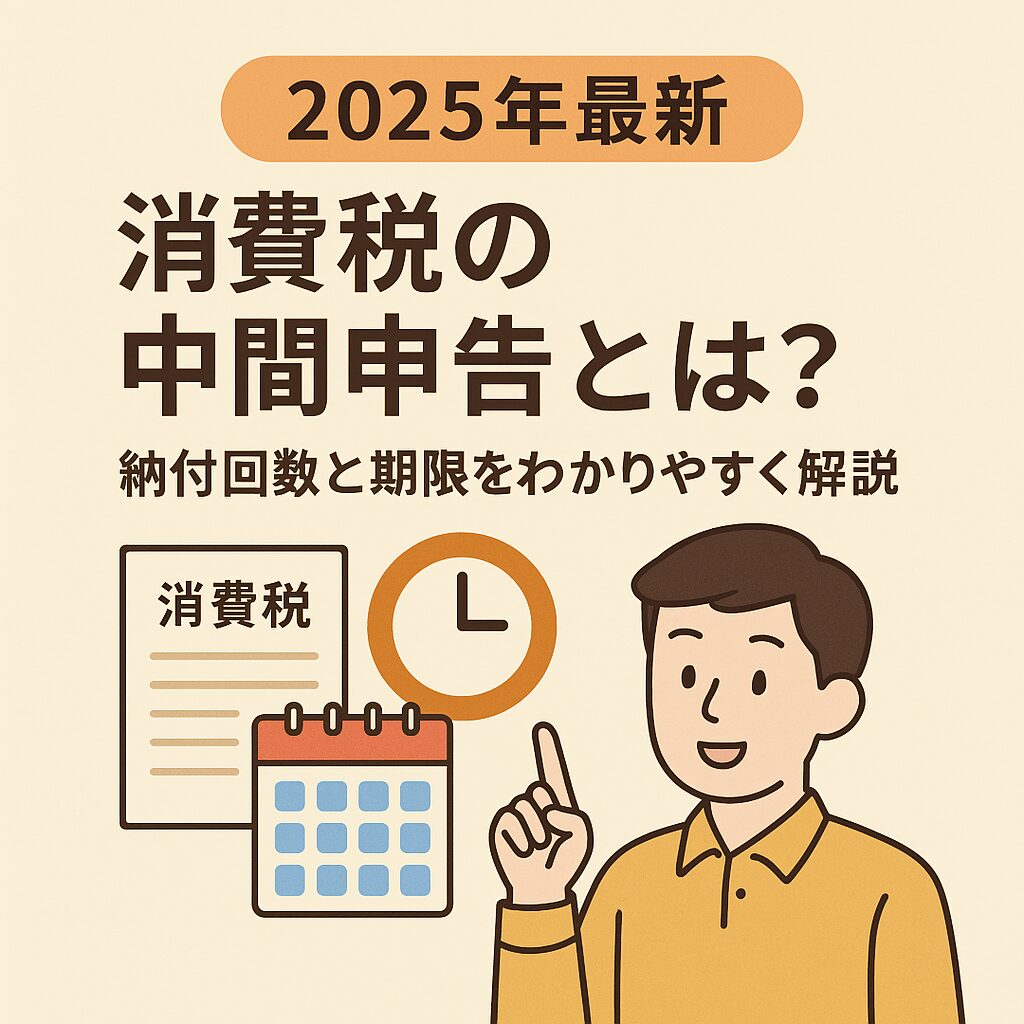「消費税の中間申告って何?」「予定納税みたいに前払いするの?」「どのくらい納めればいいの?」
多くの事業者にとって切っても切り離せない消費税。年間の確定申告だけでなく、一定の条件を満たすと年の途中でも「中間申告」をして納付しなければならないことをご存知でしょうか?
この記事では、消費税の中間申告の仕組み、対象となる事業者、申告方法、納付期限などを徹底解説します。資金繰りを左右する重要な制度ですので、ぜひ最後までご覧ください。
消費税の中間申告とは
消費税の中間申告とは、前年度の確定消費税額に基づいて、当年度の消費税を途中で前払いする制度です。所得税の予定納税と似た仕組みで、年間の税負担を分散させる目的があります。
中間申告の目的
- 国の税収の平準化: 年度末に一括で税収を得るのではなく、年間を通じて税収を確保
- 納税者の負担分散: 年度末に一度に大きな金額を納付するよりも、複数回に分けて納付することで資金繰りの負担を軽減
中間申告の対象者
中間申告が必要となるのは、前年度の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円を超える事業者です。前年度の消費税額によって、中間申告の回数や金額が異なります。
中間申告が必要となる条件
中間申告の対象となるかどうかは、前年度の確定消費税額(地方消費税を除く)で決まります。
| 前年度の確定消費税額 | 中間申告の要否 | 中間申告の回数 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 不要(任意で可能) | 年1回(任意) |
| 48万円超400万円以下 | 必要 | 年1回 |
| 400万円超4,800万円以下 | 必要 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 必要 | 年11回 |
注意すべき点として、ここでいう「確定消費税額」は地方消費税を含まない消費税額のことです。例えば、消費税(8%)と地方消費税(2%)を合わせた10%のうち、8%部分の税額だけで判定します。
中間申告の2つの方法
中間申告には、次の2つの方法があります:
- 前年実績による中間申告(原則的な方法)
- 仮決算に基づく中間申告(特例的な方法)
それぞれの特徴と適した状況を見ていきましょう。
前年実績による中間申告
前年実績による中間申告は、前年度の確定消費税額をもとに、機械的に中間納付額を計算する方法です。基本的には、この方法が一般的です。
特徴
- 税務署から「消費税の中間申告書」と「納付書」が自動的に送付される
- 納付金額はすでに記載されており、事業者側で金額の計算は不要
- 手続きが簡単で、そのまま納付することができる
向いている事業者
- 前年と今年の売上や仕入れに大きな変動がない事業者
- 事務手続きを簡略化したい事業者
仮決算に基づく中間申告
仮決算に基づく中間申告は、中間申告期間の実際の取引をもとに、確定申告と同様の方法で消費税額を計算する方法です。
特徴
- 中間申告期間(半年間など)の実際の売上・仕入れから消費税を計算
- 前年と比べて業績が大幅に変化している場合に有効
- 計算方法は確定申告と同じため、事務作業の負担が大きい
向いている事業者
- 前年よりも売上が大幅に減少している事業者
- 今年は大きな設備投資などで仕入税額控除が増える事業者
- 前年実績による申告額よりも実際の納税額が少なくなる事業者
注意点
仮決算に基づく中間申告は、必ず中間申告期限までに行わなければなりません。期限が過ぎると自動的に前年実績による中間申告の税額が適用されます。
消費税額による中間申告の納付回数と期限
前年度の確定消費税額によって、中間申告の回数と納付額、そして申告・納付期限が異なります。
前年の消費税額が48万円超400万円以下の場合
- 申告・納付回数: 年1回
- 納付額: 前年度確定消費税の約半分(前年の税額×1/2)
- 申告・納付期限: 8月31日(振替納税利用の場合は9月27日)
前年の消費税額が400万円超4,800万円以下の場合
- 申告・納付回数: 年3回
- 納付額: 前年度確定消費税の約4分の1を3回(前年の税額×1/4)
- 申告・納付期限:
- 1回目:5月31日(振替納税は6月26日)
- 2回目:8月31日(振替納税は9月27日)
- 3回目:11月30日(振替納税は12月27日)
前年の消費税額が4,800万円超の場合
- 申告・納付回数: 年11回
- 納付額: 前年度確定消費税の約12分の1を11回(前年の税額×1/12)
- 申告・納付期限:
- 1回目:3月31日(振替納税は4月26日)
- 2回目:4月30日(振替納税は5月26日)
- 3回目:5月31日(振替納税は6月26日)
- 4回目:6月30日(振替納税は7月26日)
- 5回目:7月31日(振替納税は8月23日)
- 6回目:8月31日(振替納税は9月27日)
- 7回目:9月30日(振替納税は10月25日)
- 8回目:10月31日(振替納税は11月26日)
- 9回目:11月30日(振替納税は12月27日)
- 10回目:12月31日(振替納税は1月29日)
- 11回目:1月31日(振替納税は2月26日)
※期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
法人の場合の納付期限
法人事業者の場合、事業年度の終了日(決算日)によって、中間申告と納付の期限が変わります。例えば、3月決算の法人と9月決算の法人では、中間申告の時期が異なります。
中間申告書は、原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。
任意の中間申告制度
前年の確定消費税額が48万円以下の事業者は、原則として中間申告は不要です。しかし、希望すれば任意で中間申告をすることができます。
任意の中間申告のメリット
- 年間の税負担を分散できる
- 資金繰りの平準化が可能
- 確定申告時の納付額を抑えられる
任意の中間申告の手続き
任意の中間申告をするには、「消費税の任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に提出します。この届出書は、任意の中間申告をしようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
例えば、個人事業主で2026年分から任意の中間申告をしたい場合は、2025年12月31日までに届出書を提出します。
任意の中間申告の場合、申告回数は年1回のみとなり、中間申告対象期間は、個人事業主の場合は1月1日から6月30日までの期間となります。
中間申告・納付の流れ
前年実績による中間申告の場合
- 税務署から中間申告書と納付書が送付される
- 申告書に必要事項を記入する(金額はすでに記載されている)
- 申告書を提出し、中間申告税額を納付する
仮決算に基づく中間申告の場合
- 中間申告対象期間の売上・仕入れなどの取引データを集計する
- 消費税の計算を行う(確定申告と同様の方法)
- 中間申告書に必要事項を記入する
- 申告書を提出し、計算した中間申告税額を納付する
納付方法
消費税の中間申告税額は、以下の方法で納付できます:
- 金融機関または税務署の窓口で納付
- 電子納税(e-Tax)
- 振替納税
- クレジットカード納付
よくある質問
Q1: 中間申告を忘れた場合はどうなりますか?
A: 中間申告の期限を過ぎると、延滞税がかかる場合があります。また、長期間放置すると税務署から督促状が届くことがあります。忘れていたことに気づいたら、すぐに最寄りの税務署に連絡し、対応方法を相談しましょう。
Q2: 中間申告の金額はどのように計算されますか?
A: 前年実績による中間申告の場合、前年度の確定消費税額を申告回数で割った金額になります。例えば、前年の確定消費税額が96万円で年1回の中間申告の場合、中間申告額は48万円(96万円×1/2)となります。
Q3: 赤字でも中間申告は必要ですか?
A: 中間申告の必要性は、前年度の確定消費税額で決まります。当年度が赤字でも、前年度の確定消費税額が48万円を超えていれば中間申告は必要です。ただし、今年度が大幅な赤字で消費税も少なくなりそうな場合は、仮決算に基づく中間申告を検討しましょう。
Q4: 消費税の課税事業者になったばかりですが、中間申告は必要ですか?
A: 消費税の課税事業者になって最初の年は、前年度の確定消費税額がないため、原則として中間申告は不要です。ただし、特定期間(個人事業主の場合は前年1月1日から6月30日まで、法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、初年度から中間申告が必要となることがあります。
Q5: 課税事業者を選択したばかりの個人事業主ですが、中間申告は必要ですか?
A: 基本的には、課税事業者として最初の年は中間申告は不要です。ただし、任意で中間申告をすることは可能です。資金繰りの観点から年間の税負担を分散させたい場合は、任意の中間申告を検討してみてください。
まとめ
消費税の中間申告は、前年度の確定消費税額が48万円を超える事業者に課せられる制度です。年間の税負担を分散させる目的がありますが、資金繰りに影響するため、しっかりと理解しておく必要があります。
重要ポイント
- 中間申告は前年度の確定消費税額が48万円超の事業者が対象
- 前年の消費税額によって申告回数と納付額が変わる
- 前年実績による中間申告と仮決算に基づく中間申告の2種類がある
- 前年より業績が大幅に下がっている場合は仮決算に基づく中間申告が有利
- 48万円以下の事業者も任意で中間申告可能
中間申告の制度を理解し、資金繰り計画に組み込むことで、年度末の大きな納税負担を避けることができます。自社の状況に合わせて、適切な申告方法を選びましょう。
この記事は2025年4月現在の情報に基づいて作成されています。税制は改正されることがありますので、最新情報は国税庁のWebサイトなどでご確認ください。