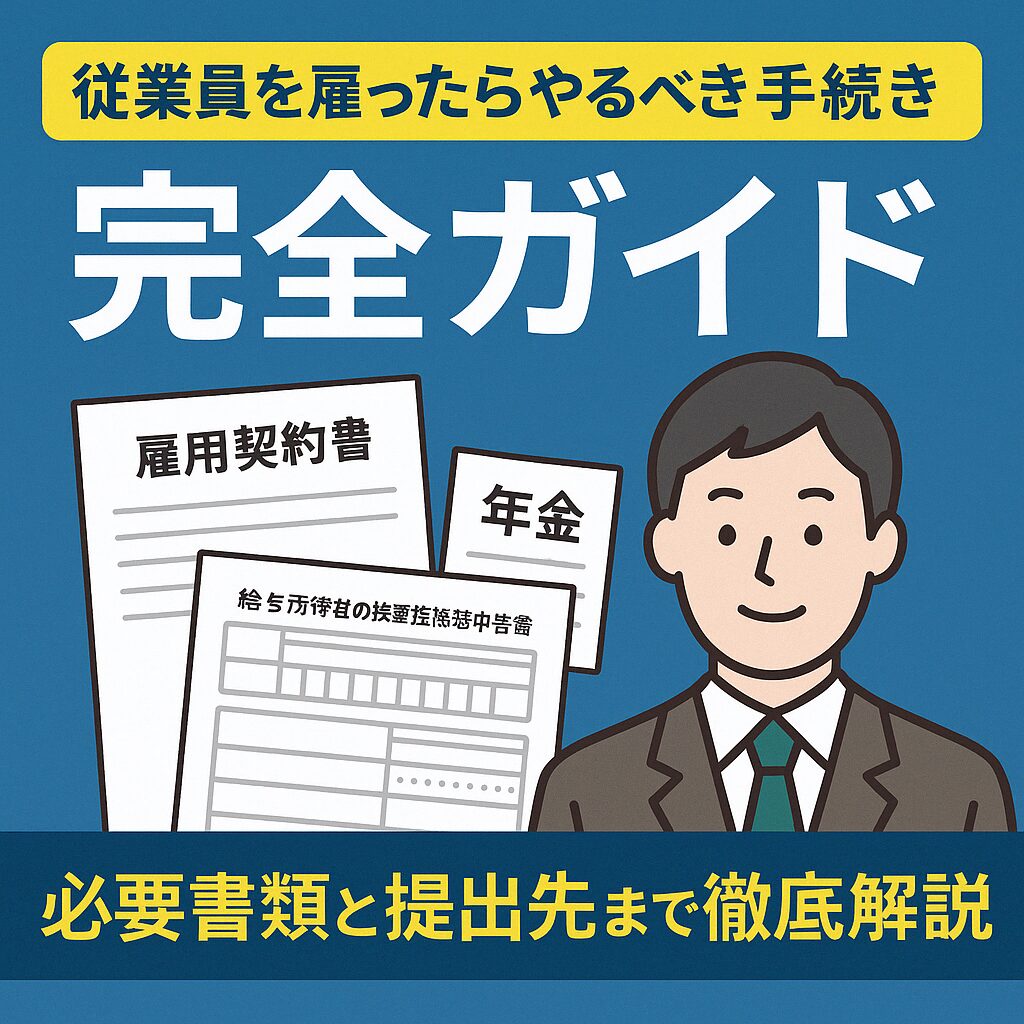「従業員を雇ったけど、どんな手続きが必要なんだろう?」「手続きを忘れていて罰則を受けたらどうしよう…」
従業員を初めて雇い入れる際、多くの事業主がこのような不安を抱えています。実際、従業員を雇用すると、税務署や年金事務所、労働基準監督署など様々な行政機関への届出義務が発生し、期限内に適切に手続きを行わないと罰則を受けるケースもあります。
本記事では、個人事業主・法人問わず、従業員を雇ったらやるべき5つの重要手続きについて、必要書類や提出先、期限までを専門家監修のもと徹底解説します。手続き漏れによるトラブルを避け、安心して事業に集中できるよう、この記事を参考にしてください。
従業員雇用時に必要な手続き一覧
従業員を雇い入れた際に必要な手続きは、主に以下の5つです。それぞれ提出先が異なるため、注意が必要です。
| 手続き | 提出先 | 提出期限 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|---|---|
| 源泉所得税関連 | 税務署 | 給与支払開始日から1ヶ月以内 | 必須 | 必須 |
| 労災保険関連 | 労働基準監督署 | 従業員雇用の翌日から10日以内 | 必須 | 必須 |
| 雇用保険関連 | ハローワーク | 従業員雇用の翌日から10日以内 | 必須※ | 必須※ |
| 社会保険関連 | 年金事務所 | 従業員雇用の翌日から5日以内 | 必須 | 条件付き |
| 住民税関連 | 市区町村 | 随時(給与支払開始後速やかに) | 必須 | 必須 |
※雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入義務があります
それでは、各手続きの詳細と必要書類について解説していきます。
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
- 労働保険関係成立届(様式第1号)
- 労働保険概算保険料申告書(様式第6号)
- 雇用保険適用事業所設置届(様式第1号)
- 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上の雇用見込み
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(様式第1号)または任意適用申請書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 法人:従業員数に関わらず必須
- 個人事業主:常時5人以上の従業員を雇用している場合
- 給与所得者異動届出書または特別徴収への切替申請書
- 総従業員数が2人以下
- 給与が少なく税金が引けない
- 給与の支払いが不定期
- 退職者または退職予定者
税務署への届出(源泉所得税関連)
従業員を雇い入れた際、まず最初に行うべきなのが税務署への届出です。従業員に給与を支払う事業主は「源泉徴収義務者」となり、従業員の給料から所得税を差し引いて納付する義務が生じます。
提出が必要な書類
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 目的:源泉徴収義務者として税務署に登録するための書類
- 提出期限:給与の支払いを開始してから1ヶ月以内
- 必要事項:事業主の情報、事業所の所在地、給与支払開始日など
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
- 目的:源泉所得税の納付を毎月から年2回に変更できる特例の申請
- 提出期限:特に定めなし(特例適用を受けたい時期の前に提出)
- メリット:事務負担の軽減(毎月10日の納付が年2回で済む)
源泉所得税の納付方法
源泉所得税は基本的に毎月従業員の給料から差し引いた分を翌月10日までに納付する必要があります。ただし、「納期の特例」を申請すると以下のように納付回数が減ります:
- 1月〜6月分:7月10日までに納付
- 7月〜12月分:翌年1月20日までに納付
特に従業員数が少ない事業主にとっては、納期の特例を利用することで事務負担を大幅に軽減できるため、積極的に検討するとよいでしょう。
源泉所得税の計算方法
源泉所得税の計算は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて行います。計算方法は従業員の給与額や扶養家族の数によって異なります。詳しい計算方法や最新の税率については、国税庁のホームページで確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
労働基準監督署への届出(労災保険関連)
労災保険は、従業員が業務上の事故や通勤途中の事故でケガをした場合に補償する保険制度です。従業員を1人でも雇った時点で、個人事業主・法人問わず、加入が義務付けられています。
提出が必要な書類
- 労働保険関係成立届(様式第1号)
- 目的:労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
- 提出期限:従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内
- 必要事項:事業の種類、労働者数、事業場の所在地など
- 労働保険概算保険料申告書(様式第6号)
- 目的:当年度の概算保険料を申告・納付するための書類
- 提出期限:労働保険関係成立届と同時
- 必要事項:賃金総額の見込み額、保険料率など
労災保険料の計算方法
労災保険料は、従業員に支払う賃金総額に業種ごとの保険料率をかけて計算します。保険料率は業種によって異なり、危険度の高い業種ほど料率が高くなります。
例えば、2025年度の場合:
- 小売業:1000分の2.5(0.25%)
- 飲食店:1000分の3(0.3%)
- 建設業:1000分の12(1.2%)
【注意】労災保険料は全額事業主負担です。従業員の給料から天引きすることはできません。
ハローワークへの届出(雇用保険関連)
雇用保険は、従業員が失業した際の生活保障や、育児・介護休業時の給付など様々な保障を提供する制度です。一定条件を満たす従業員は加入が必要です。
雇用保険の加入条件
雇用保険は以下の条件を満たす従業員は加入が必要です:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
パートやアルバイトでも上記条件を満たせば加入が必要です。
提出が必要な書類
- 雇用保険適用事業所設置届(様式第1号)
- 目的:事業所を雇用保険適用事業所として登録する
- 提出期限:従業員を雇用した日から10日以内
- 必要事項:事業所の名称、所在地、資本金、従業員数など
- 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 目的:従業員を雇用保険に加入させる手続き
- 提出期限:従業員を雇用した日から10日以内
- 必要事項:従業員の氏名、住所、生年月日、雇用年月日など
雇用保険料の計算方法
雇用保険料は従業員の賃金総額に保険料率をかけて計算します。料率は業種によって異なります。
2025年度の一般の事業の場合:
- 事業主負担:1000分の6.5(0.65%)
- 従業員負担:1000分の4(0.4%)
- 合計:1000分の10.5(1.05%)
【ポイント】雇用保険料は事業主と従業員が分担して負担します。従業員負担分は給与から控除できます。
年金事務所への届出(社会保険関連)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務は、法人と個人事業主で異なります。
社会保険の加入条件
- 法人:従業員数に関わらず、すべての法人は加入義務あり
- 個人事業主:常時5人以上の従業員を雇用している場合のみ加入義務あり
個人事業主で従業員が5人未満の場合は任意適用事業所として加入することも可能です。
提出が必要な書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(様式第1号)または任意適用申請書
- 目的:事業所を社会保険適用事業所として登録する
- 提出期限:従業員を雇用した日から5日以内
- 必要事項:事業所の名称、所在地、業種、従業員数など
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 目的:従業員を健康保険・厚生年金保険に加入させる手続き
- 提出期限:従業員を雇用した日から5日以内
- 必要事項:従業員の氏名、住所、生年月日、報酬額など
社会保険料の計算方法
社会保険料は従業員の標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。
2025年度の場合:
- 健康保険料:約10%(都道府県によって異なる)
- 厚生年金保険料:18.3%
上記保険料は事業主と従業員が折半で負担します(各約半分ずつ)。従業員負担分は給与から控除できます。
市区町村への届出(住民税関連)
住民税は従業員が住んでいる市区町村に納める税金です。原則として、事業主が従業員の給与から住民税を差し引き、市区町村に納める「特別徴収」を行う必要があります。
提出が必要な書類
給与所得者異動届出書または特別徴収への切替申請書
- 目的:従業員の住民税を給与から差し引く「特別徴収」の手続き
- 提出先:従業員が住民登録している市区町村
- 提出期限:特に定めはないが、雇用後速やかに
特別徴収が不要なケース
以下の場合は特別徴収ではなく、従業員自身が納付する「普通徴収」が認められることがあります:
- 給与の支払いが不定期
- 2か月以上にわたり休職している
- 給与が少なく税額が引ききれない
- 退職予定者
- 他の事業所で特別徴収されている
- 総従業員数が2人以下の個人事業主
ただし、上記の場合でも市区町村から特別徴収を求められることがあります。
必要書類一覧と入手方法
各手続きに必要な書類は、主に以下の方法で入手できます:
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届出書 従業員に給与を支払う事業所として登録 | 税務署 | 1ヶ月以内 | ||
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税の納付を年2回に変更(任意) | 税務署 | 随時 | ||
| 労働保険関係成立届(様式第1号) 労災保険・雇用保険への加入手続き | 労働基準監督署 | 10日以内 | ||
| 労働保険概算保険料申告書(様式第6号) 労働保険料の申告・納付 | 労働基準監督署 | 10日以内 | ||
| 雇用保険適用事業所設置届(様式第1号) 事業所を雇用保険適用事業所として登録 | ハローワーク | 10日以内 | ||
| 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号) 従業員を雇用保険に加入させる手続き | ハローワーク | 10日以内 | ||
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届(様式第1号) 事業所を社会保険適用事業所として登録 | 年金事務所 | 5日以内 | ||
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第2号) 従業員を健康保険・厚生年金に加入させる手続き | 年金事務所 | 5日以内 | ||
| 給与所得者異動届出書 従業員の住民税を給与から差し引く手続き | 市区町村 | 速やかに |
書類の入手方法
- e-Gov(電子政府の総合窓口)
- 労働保険関連や雇用保険関連の書類をダウンロード可能
- URL: https://www.e-gov.go.jp/
- 国税庁ホームページ
- 源泉所得税関連の書類をダウンロード可能
- URL: https://www.nta.go.jp/
- 日本年金機構ホームページ
- 社会保険関連の書類をダウンロード可能
- URL: https://www.nenkin.go.jp/
- 各市区町村のホームページ
- 住民税特別徴収関連の書類をダウンロード可能
電子申請の活用
近年は「e-Gov」や「GビズID」を利用した電子申請が推奨されています。電子申請のメリットは以下の通りです:
- 24時間365日申請可能
- 窓口に行く手間が省ける
- 申請書類の記入ミスが減る
- 申請履歴を確認できる
特に複数の従業員を雇用している場合は、電子申請の活用を検討することをおすすめします。
手続き漏れによるリスクと罰則
各種手続きを期限内に行わなかった場合、以下のようなリスクや罰則があります:
- 源泉所得税関連
- 無申告加算税:納付すべき税額の15%〜20%
- 延滞税:年7.3%〜14.6%
- 労災保険関連
- 追徴金:未納保険料の10%
- 従業員が労災事故に遭った場合、事業主が全額負担するリスク
- 雇用保険関連
- 過去2年分まで遡って保険料を徴収される
- 従業員が失業給付を受けられないリスク
- 社会保険関連
- 過去2年分まで遡って保険料を徴収される
- 加入していなかった期間の給付が受けられないリスク
- 住民税関連
- 従業員との間でトラブルになるリスク
- 市区町村から是正勧告を受けるリスク
手続き漏れによるリスクを避けるため、従業員を雇ったらすぐに必要な手続きを行うことが重要です。
💼 給与計算に悩む個人事業主・法人の方へ
給与計算や源泉徴収の対応に手間取っていませんか?
「弥生給与 NEXT」なら、クラウドでの給与処理がかんたん・確実に。
外注費との区分があいまいになりがちなケースでも自動計算・チェック機能で税務リスクを低減できます。
よくある質問
Q1: 家族従業員の場合も同じ手続きが必要ですか?
A: 基本的には同じ手続きが必要ですが、一部例外があります。
- 配偶者や親族を雇用する場合:源泉所得税や労災保険は原則として必要です
- 個人事業主の同居の親族(専従者):
- 青色申告の場合:源泉所得税は不要、労災保険は必要
- 白色申告の場合:要件によって異なる
Q2: パートやアルバイトも手続きが必要ですか?
A: 勤務時間や雇用期間によって異なります。
- 源泉所得税:給与額によって異なる(103万円以下でも徴収が必要なケースあり)
- 労災保険:1人でも雇ったら加入義務あり
- 雇用保険:週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合
- 社会保険:週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上など、一定条件を満たす場合
Q3: 手続きは自分でできますか?それとも専門家に依頼すべきですか?
A: 少人数の従業員であれば自分で行うことも可能ですが、以下の場合は専門家への依頼をおすすめします:
- 複数の従業員を一度に雇用する場合
- 複雑な給与体系がある場合
- 就業規則や雇用契約書の作成も必要な場合
- 税務・労務に関する知識や時間が不足している場合
社会保険労務士や税理士に依頼することで、手続きの漏れを防ぎ、正確かつ効率的に進めることができます。
Q4: 在宅勤務の従業員も同じ手続きが必要ですか?
A: はい、勤務場所に関わらず同じ手続きが必要です。在宅勤務でも雇用関係があれば、各種保険への加入義務や源泉徴収義務は変わりません。
- 従業員の住所、氏名、生年月日
- マイナンバー(必要に応じて)
- 扶養家族の情報(社会保険用)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 労働保険関係成立届(様式第1号)
- 労働保険概算保険料申告書(様式第6号)
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
- 給与所得者異動届出書
- 特別徴収への切替申請書
- 就業規則の作成・変更届(10人以上の場合)
- 36協定届(時間外労働がある場合)
- 雇用契約書の締結
まとめ:従業員を雇ったら速やかに手続きを
従業員を雇ったら行うべき手続きは多岐にわたりますが、期限内に適切に対応することで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に初めて従業員を雇う場合は不安も多いと思いますが、以下のポイントを押さえておきましょう:
- 期限を守る:各手続きには提出期限があります
- 必要書類を漏れなく準備:事前に必要書類を確認しておく
- 専門家に相談する:不明点があれば早めに専門家に相談する
- 電子申請を活用する:窓口に行く手間を省き、効率的に手続きを進める
これらのポイントを押さえて、従業員との良好な関係を築きながら、安心して事業を運営していきましょう。
また、従業員の給与計算や社会保険料計算などの労務管理を効率化するなら、クラウド型の労務管理ソフトの導入もご検討ください。
💼 給与計算に悩む個人事業主・法人の方へ
給与計算や源泉徴収の対応に手間取っていませんか?
「弥生給与 NEXT」なら、クラウドでの給与処理がかんたん・確実に。
外注費との区分があいまいになりがちなケースでも自動計算・チェック機能で税務リスクを低減できます。