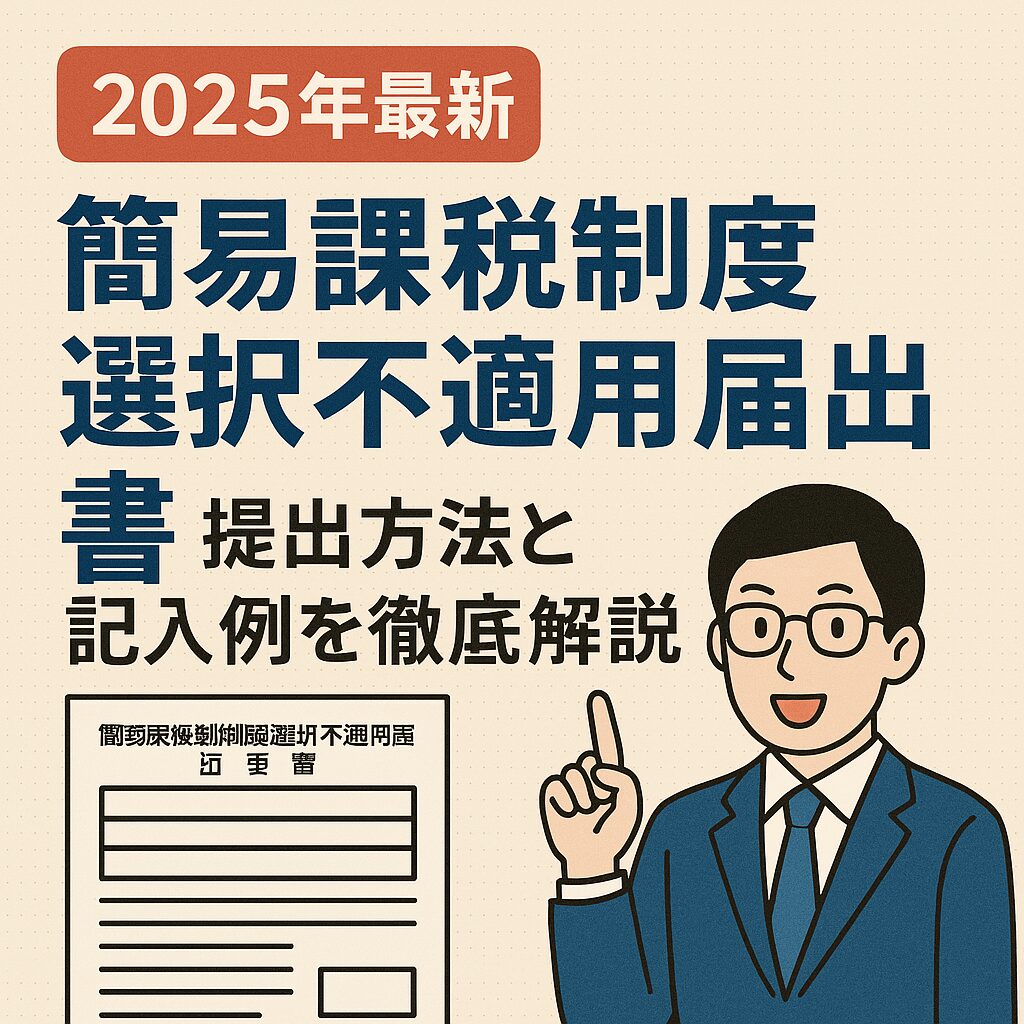消費税の簡易課税制度を利用しているが、本則課税に戻したい場合はどうすればよいのでしょうか?そんなときに必要となるのが「簡易課税制度選択不適用届出書」です。この記事では、届出書の概要から記入方法、提出期限まで、個人事業主やフリーランスの方にもわかりやすく解説します。
簡易課税制度選択不適用届出書とは
「簡易課税制度選択不適用届出書」とは、現在消費税の簡易課税制度を適用している事業者が、その適用をやめて本則課税方式に戻すために提出する届出書です。
簡易課税制度は、売上に対する消費税額から「みなし仕入率」を使って納税額を計算するシンプルな方法ですが、状況によっては本則課税のほうが有利になる場合もあります。そのような場合に、簡易課税から本則課税に切り替えるために必要な手続きです。
届出書の提出が必要な方
次のすべての条件に当てはまる方が届出の対象となります:
- 現在、消費税の納税において「簡易課税制度」を適用している
- 今後、「本則課税方式」に切り替えたい
- 簡易課税制度の適用開始から2年以上が経過している
提出期限と注意点
提出期限
本則課税に戻したい課税期間(年度)の初日の前日までに提出する必要があります。
例えば、個人事業主の場合:
- 2026年(令和8年)1月1日から本則課税に戻したい場合
- 提出期限は2025年(令和7年)12月31日まで
法人の場合:
- 決算期が3月の法人で、2026年4月1日から本則課税に戻したい場合
- 提出期限は2026年3月31日まで
重要な注意点:2年間の継続適用ルール
消費税の簡易課税制度は、選択してから最低2年間は継続して適用することが法律で定められています。
このため、簡易課税を選択してから2年経過するまでは、本届出書を提出することができません。例えば、2023年から簡易課税を選択した場合、最短で2025年分から本則課税に戻すことができます。
届出書の入手方法
簡易課税制度選択不適用届出書は、以下の方法で入手できます:
1. 税務署で直接入手する
最寄りの税務署に行き、窓口で「簡易課税制度選択不適用届出書」を請求します。その場で記入して提出することも可能です。
2. 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページからPDFファイルをダウンロードして印刷できます。以下の手順で探すことができます:
- 国税庁ホームページにアクセス
- 「税務手続・用紙(手続・用紙の案内)」をクリック
- 「申告・申請・届出等、用紙(手続の案内)」をクリック
- 「消費税関係」から探す
3. 会計ソフトを使用して電子申告する(おすすめ)
会計ソフトを利用すると、以下のメリットがあります:
- PC上で簡単に作成できる
- 計算ミスを防止できる
- 電子申告(e-Tax)ができ、税務署への持参や郵送の手間が省ける
- 提出履歴が電子的に保管される
主要な会計ソフト(freee、マネーフォワードクラウド会計など)であれば、簡易課税制度選択不適用届出書の作成・申請が可能です。
簡易課税制度選択不適用届出書の記入方法
以下、届出書の主要な記入項目と記入のポイントを解説します。
記入のポイント
- 1. 所轄税務署名
自分の納税地を管轄する税務署名を記入します。納税地に関する詳細は、住所地・居所地・事業所所在地の違いとは?確定申告での正しい納税地の選び方を参照してください。 - 2. 納税地、氏名・名称等
税務署に納税地として届け出ている場所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、個人番号(法人の場合は法人番号)を記入します。 - 3. 適用をやめようとする課税期間
簡易課税の適用をやめて本則課税に戻したい期間の開始日と終了日を記入します。
例:2026年1月1日から2026年12月31日まで(個人事業主の場合) - 4. 基準期間における課税売上高
適用をやめようとする課税期間の前々年(基準期間)の課税売上高を記入します。この金額は税抜きで記入します。
例:2026年分の申告から簡易課税をやめる場合、2024年の課税売上高を記入 - 5. 簡易課税制度の適用を受けることとなった課税期間の初日
簡易課税制度を最初に適用した課税期間の初日を記入します。わからない場合は税務署に確認するか、空欄のままでも構いません。 - 6. 事業を廃止した場合
事業を廃止した場合には、廃業日を記入します。個人事業主の場合は、マイナンバー(個人番号)の記入も必要です。
記入例

提出後の流れと影響
簡易課税制度選択不適用届出書を提出すると、指定した課税期間から本則課税に戻ります。これにより、以下のような変化が生じます:
1. 消費税の計算方法が変わる
- 簡易課税: 売上にかかる消費税額 × (1 - みなし仕入率)
- 本則課税: 売上にかかる消費税額 - 仕入れにかかる消費税額
2. 経理処理の変更が必要
本則課税では、すべての課税仕入れに関する帳簿と請求書等を保存し、消費税額を正確に計算する必要があります。
3. 節税効果の変化
実際の仕入税額の割合がみなし仕入率より高い場合は、本則課税のほうが税負担が軽くなる可能性があります。逆に、実際の仕入税額の割合がみなし仕入率より低い場合は、簡易課税のほうが有利でした。
よくある質問(Q&A)
Q1: 簡易課税の適用を受けていたのですが、今回消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を提出しました。簡易課税制度の適用も今後取り消しとなりますか?
A: 「簡易課税制度の届出」の効力は「納税義務者でなくなった旨の届出」の提出によっては失効しません。翌期以降に再び課税事業者に該当することとなっても、改めて「簡易課税制度の届出」をする必要はなく、簡易課税の適用を受けることが可能です。 (参照:国税不服審判所 判例No.51-731項)
Q2: 2年間の継続適用期間中でも、届出書を提出できる場合はありますか?
A: 原則として、簡易課税制度の選択から2年経過するまでは不適用届出書を提出することはできません。ただし、事業を廃止する場合は例外的に2年未満でも提出できます。
Q3: 簡易課税から本則課税に戻した後、再び簡易課税に戻すことはできますか?
A: はい、可能です。ただし、再び簡易課税を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。また、再度選択した場合も2年間の継続適用ルールが適用されます。
Q4: 届出書の提出を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A: 提出期限(適用をやめようとする課税期間の初日の前日)までに届出書を提出しなかった場合、その課税期間は引き続き簡易課税制度が適用されます。本則課税に戻すのは、次の課税期間からとなります。
Q5: 法人成り(個人から法人への変更)をした場合、簡易課税の適用はどうなりますか?
A: 法人成りした場合、法人は新たな納税者となるため、個人時代の簡易課税の選択は引き継がれません。法人として簡易課税の適用を受けたい場合は、新たに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
まとめ
簡易課税制度選択不適用届出書は、簡易課税制度から本則課税に戻るための重要な手続きです。以下のポイントを覚えておきましょう:
- 2年間の継続適用ルール: 簡易課税を選択したら、最低2年間は継続適用が必要
- 提出期限: 本則課税に戻したい課税期間の初日の前日まで
- 効果: 指定した課税期間から本則課税方式で消費税を計算
- 判断基準: 実際の仕入税額の割合がみなし仕入率より高い場合は本則課税が有利
自分のビジネスの状況に応じて、簡易課税と本則課税のどちらが有利かを定期的に検討し、必要に応じて切り替えを検討しましょう。不明点がある場合は、税理士や最寄りの税務署に相談することをおすすめします。
この記事は2025年4月現在の税制に基づいて作成されています。税制は改正されることがありますので、最新情報は国税庁のWebサイトなどでご確認ください。