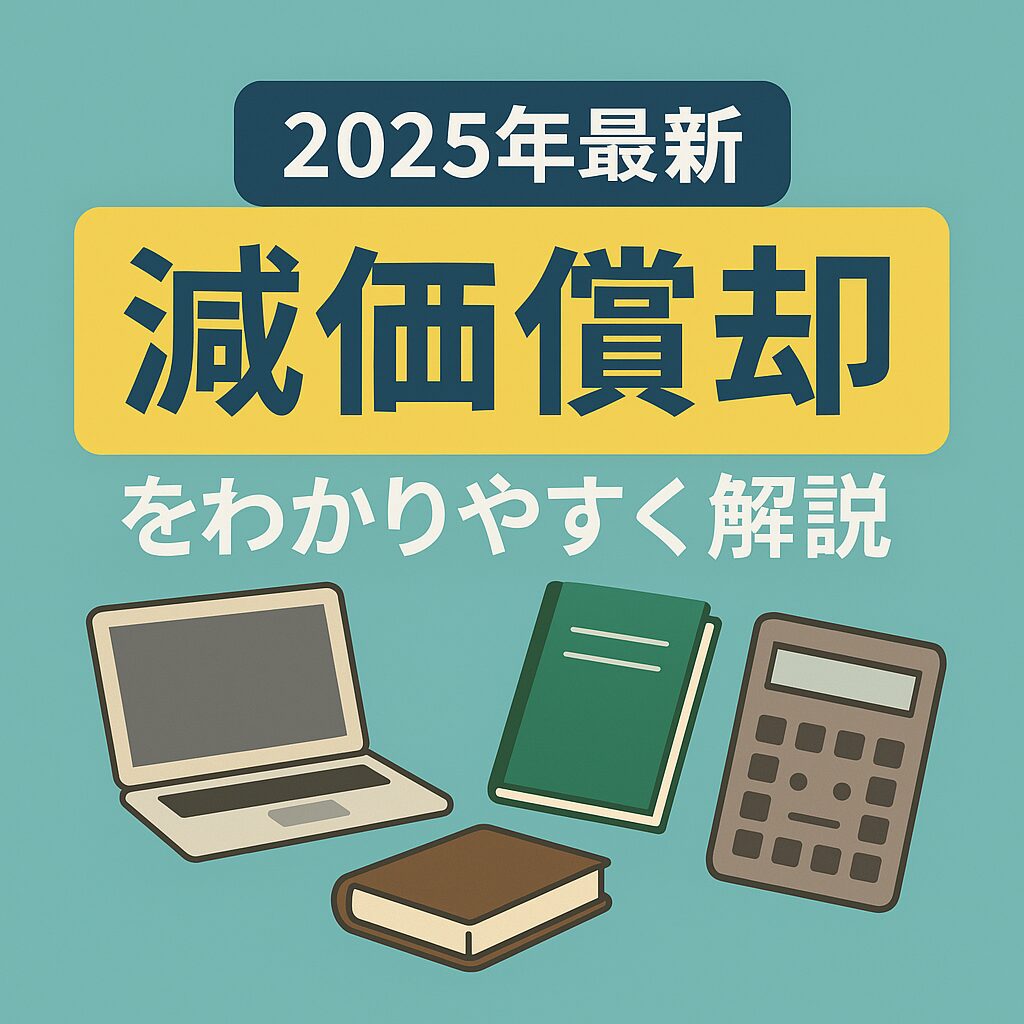はじめに:減価償却は難しくない!
「高額な機材を購入したけど、買った年に全部経費にできないの?」
「減価償却って何?会計用語が難しくて理解できない…」
個人事業主や小規模事業者としてビジネスを始めると、こうした疑問や不安が出てくるものです。確かに「減価償却」という言葉は少し難しく感じるかもしれませんが、仕組み自体はとてもシンプルです。
この記事では、会計の専門知識がなくても理解できるよう、減価償却の基本的な考え方から確定申告での具体的な処理方法まで、図解を交えてわかりやすく解説します。これを読めば、確定申告の際に自信を持って減価償却を活用できるようになります。
減価償却とは?|ざっくり説明
減価償却とは、簡単に言えば「高額な設備や備品の費用を、使用する年数に分けて少しずつ経費にしていく仕組み」です。
減価償却の基本
- 高額な備品・設備は、購入した年に全額を経費にすることはできません
- 「数年かけて、少しずつ経費にしていく」必要があります
- この「少しずつ経費計上していく」仕組みを「減価償却」と呼びます
つまり、減価償却は「高額な買い物の費用を分割して処理する方法」 と考えると理解しやすいでしょう。
例えば、20万円のパソコンを購入した場合、一度に20万円を経費にするのではなく、4年間かけて毎年5万円ずつ経費として計上していきます。
減価償却が必要な理由
なぜ高額な資産は一度に経費にできず、減価償却が必要なのでしょうか?
会計上の正確性を保つため
高額な設備や備品は、購入した年だけでなく、何年にもわたって事業に貢献します。その貢献(価値)は時間とともに少しずつ減っていくと考えられています。
例えば、業務用パソコンは購入直後から価値が徐々に下がり、通常4年程度で買い替えることが多いでしょう。パソコンの価値がこのように徐々に減少していくことを会計上で表現するのが減価償却なのです。
税負担の平準化
もし高額な設備投資をすべて購入年の経費にできてしまうと、その年の利益が極端に少なく(または赤字に)なる可能性があります。逆に翌年以降は設備投資の経費がないため、利益が多く出ることになります。
減価償却によって費用を分散させることで、毎年の利益と税負担を平準化する効果があるのです。
どんなものが減価償却の対象になるのか
減価償却の対象となる資産(減価償却資産)には、どのようなものがあるのでしょうか?
基本的な条件
減価償却の対象となる資産は、以下の条件を満たすものです:
- 10万円以上の取得価額があること
- 事業のために使用するものであること
- 耐用年数が1年以上のもの(長期間使用するもの)
主な減価償却資産の例と耐用年数
| 資産の種類 | 具体例 | 一般的な耐用年数 |
|---|---|---|
| パソコン・周辺機器 | デスクトップPC、ノートPC、プリンター | 4年 |
| 事務機器 | コピー機、シュレッダー | 5年 |
| カメラ機材 | デジタルカメラ、ビデオカメラ | 5年 |
| 車両 | 乗用車、トラック | 4~6年 |
| 家具・什器 | オフィス家具、応接セット | 8年 |
| 内装・設備 | 店舗の内装工事、看板 | 10~15年 |
| ソフトウェア | 会計ソフト、業務用アプリ | 5年 |
※耐用年数は資産の種類や用途によって異なります。詳細は国税庁の「減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。
減価償却の対象にならないもの
以下のようなものは、減価償却の対象にはなりません:
- 消耗品(文房具、事務用品など)
- 取得価額が10万円未満のもの(一部例外あり)
- 土地(価値が減少しないため)
- 商品(販売目的のもの)
10万円未満のものは、購入した年に「消耗品費」として全額経費計上できます。
耐用年数とは|減価償却の期間を決める基準
耐用年数とは、その資産が使用に耐えられると見込まれる年数のことで、減価償却を行う期間を決める重要な基準です。
耐用年数の決まり方
耐用年数は、資産の種類や材質、用途などによって法律(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)で定められています。事業者が自由に決めることはできません。
たとえば、同じパソコンでも、家庭で使用する場合と事業で使用する場合では、耐用年数が異なることがあります。
主な事業用資産の耐用年数例
- デスクトップパソコン:4年
- ノートパソコン:4年
- スマートフォン・タブレット:4年
- オフィス家具(机・椅子):8年
- 一般乗用車:6年(軽自動車は4年)
- エアコン:6年
- デジタルカメラ:5年
- 事務用ソフトウェア:5年
事業で使用する資産の耐用年数の詳細については、国税庁のWebサイトで確認することができます。
特例:少額減価償却資産の特例(即時償却)
通常は10万円以上の資産は減価償却が必要ですが、特例により一定の条件下では購入年に全額経費計上できる制度があります。
少額減価償却資産の特例の概要
- 10万円未満の資産:通常の消耗品として、購入年に全額経費計上可能
- 30万円未満の資産:青色申告者限定で"一括償却"(即時償却)が可能
これを「少額減価償却資産の特例」と言います。
特例適用の条件
- 青色申告をしていること
- 資産の取得価額が10万円以上30万円未満であること
- 年間の適用限度額は合計300万円まで
- 対象資産を事業のために使用していること
特例を使うメリット
この特例を使うと、本来なら数年かけて経費計上する資産を、購入した年にまとめて経費にできるため、その年の所得と税金を減らすことができます。
特に設備投資を行った年は経費が大きくなるため、節税効果が期待できるでしょう。
注意点
- 白色申告の場合は、10万円以上30万円未満の資産でも減価償却が必要です
- 年間300万円を超える部分は通常の減価償却となります
- 特例の適用を受けるには、確定申告書に明細の添付が必要です
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法には主に「定額法」と「定率法」の2種類がありますが、2025年現在、個人事業主は原則として「定額法」を使用します。
① 定額法(基本的な計算方法)
定額法とは、毎年同じ金額を経費として計上する方法です。計算式は以下の通りです:
年間の減価償却費 = (取得価額 - 残存価額)÷ 耐用年数※2007年4月1日以降に取得した資産については、残存価額は0円(備忘価額1円)となっています。
定額法の計算例
20万円のパソコン(耐用年数4年)を購入した場合:
年間の減価償却費 = 200,000円 ÷ 4年 = 50,000円/年つまり、4年間にわたって毎年5万円ずつ経費として計上します。
② 定率法(参考)
定率法は、最初の年に多くの減価償却費を計上し、年々その金額を減らしていく方法です。現在、個人事業主は原則として使用できなくなっていますが、過去に取得した一部の資産では使用されている場合があります。
減価償却の計算例(まとめ)
以下に、定額法での減価償却の計算例をまとめます:
| 年度 | 減価償却費 | 期首簿価 | 期末簿価 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 50,000円 | 200,000円 | 150,000円 |
| 2年目 | 50,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
| 3年目 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
| 4年目 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
※実際には4年目の期末簿価は備忘価額として1円残します。
確定申告での減価償却の処理方法
減価償却資産を取得したら、確定申告でどのように処理すればよいのでしょうか?
減価償却資産台帳の作成と記録
減価償却資産を取得したら、「減価償却資産台帳」に記録する必要があります。台帳には以下の情報を記載します:
- 資産の名称
- 取得年月日
- 取得価額
- 耐用年数
- 償却方法(定額法など)
- 毎年の減価償却費
- 帳簿価額の推移
台帳はExcelなどで自作することもできますし、会計ソフトを使えば自動的に作成・管理できます。
青色申告決算書への記入方法
青色申告の場合、減価償却費は以下のように記載します:
- 貸借対照表:減価償却資産は「固定資産」として記載
- 減価償却費の計算明細書:資産ごとの減価償却の計算内容を記載
- 損益計算書:「減価償却費」の欄に合計金額を記入
白色申告での記入方法
白色申告の場合は、収支内訳書の「減価償却費」欄に金額を記入します。ただし、白色申告でも減価償却資産の管理は必要です。
会計ソフトを使った管理
会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使用すると、減価償却の計算や台帳管理が自動化されるため、非常に便利です。
会計ソフトを使うと、以下のようなメリットがあります:
- 耐用年数の自動判定
- 減価償却費の自動計算
- 減価償却資産台帳の自動作成
- 確定申告書類への自動反映
特に確定申告時の作業が大幅に効率化されるため、会計に不慣れな個人事業主の方にはおすすめです。
減価償却に関するよくある質問
Q1. 白色申告でも減価償却はできますか?
A: はい、白色申告でも減価償却は必要です。ただし、30万円未満の資産に対する「少額減価償却資産の特例」(一括償却)は青色申告者限定の特例なので、白色申告の場合はこの特例を利用できません。
Q2. 事業と私用の両方で使う資産(パソコンなど)はどうすればいいですか?
A: 事業と私用の両方で使用する資産は、その使用割合に応じて減価償却費を計算します。例えば、パソコンを事業で70%、私用で30%使用する場合、減価償却費の70%のみを経費として計上できます。
Q3. 年の途中で資産を購入した場合はどうなりますか?
A: 年の途中で購入した場合、その年の減価償却費は「月割り」で計算します。例えば、8月に購入した場合、初年度は5ヶ月分(8月〜12月)の減価償却費を計上します。
初年度の減価償却費 = 年間の減価償却費 × 使用月数 ÷ 12ヶ月
Q4. 減価償却資産を売却した場合はどうなりますか?
A: 減価償却資産を売却した場合、「売却価格」と「売却時点の帳簿価額(簿価)」の差額が「譲渡損益」となります。
- 売却価格 > 簿価 → 譲渡益(利益)が発生
- 売却価格 < 簿価 → 譲渡損(損失)が発生
この譲渡損益は、確定申告で申告する必要があります。
Q5. 途中で使わなくなった資産はどうすればいいですか?
A: 使用しなくなった資産は「除却」として処理します。除却した資産の簿価は、その時点で損失(除却損)として計上できます。
Q6. 中古品を購入した場合の耐用年数はどうなりますか?
A: 中古資産の耐用年数は、以下のいずれか短い年数になります。
- 法定耐用年数 × 0.8
- 法定耐用年数 - 経過年数
- 2年
多くの場合、ある程度使用された中古品は、新品より短い耐用年数が適用されます。
減価償却の管理・計算を簡単に!おすすめの会計ソフト
減価償却の計算や管理が複雑に感じる方も多いのではないでしょうか。特に複数の資産を所有している場合や、年度をまたいだ管理は手作業だと煩雑になりがちです。
そんな方におすすめなのが、マネーフォワード クラウド確定申告です。
マネーフォワード クラウド確定申告のメリット
- 減価償却費を自動計算:資産情報を入力するだけで、耐用年数に応じた減価償却費を自動計算
- 減価償却資産台帳を自動作成:資産の購入から除却までを一元管理
- 少額減価償却資産の特例も対応:青色申告の特例適用条件も自動チェック
- 確定申告書類に自動反映:計算した減価償却費が青色申告決算書に自動で反映
プログラミングの知識は不要で、画面の案内に従って入力するだけなので、会計知識が少ない方でも安心して使えます。
また、銀行口座やクレジットカードとの連携機能により、日々の経費計上も格段に効率化。事業に集中できる時間が増えます。
実際に多くのひとり起業家や個人事業主の方々が、マネーフォワードの導入で確定申告の準備時間を大幅に削減しています。年間の税金管理だけでなく、日々の経営判断にも役立つ会計ソフトを、ぜひお試しください。
まとめ:減価償却は"高額な経費の分割払い"
減価償却は難しく感じるかもしれませんが、要するに「高額な経費の分割払い」と考えれば理解しやすいでしょう。
ポイントおさらい
- 10万円以上の事業用資産は、耐用年数に沿って少しずつ経費にする
- 青色申告なら「少額減価償却資産の特例」(30万円未満の即時償却)が使えて有利
- 会計ソフトを活用すれば、減価償却も自動計算されるのでカンタン
- 減価償却資産台帳で適切に管理することが重要
減価償却は、事業の実態を正確に反映し、適切な節税効果をもたらす重要な会計処理です。この記事の内容をマスターして、スムーズな確定申告に役立ててください。
関連記事
この記事は2025年4月現在の税制に基づいて作成されています。税制改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。