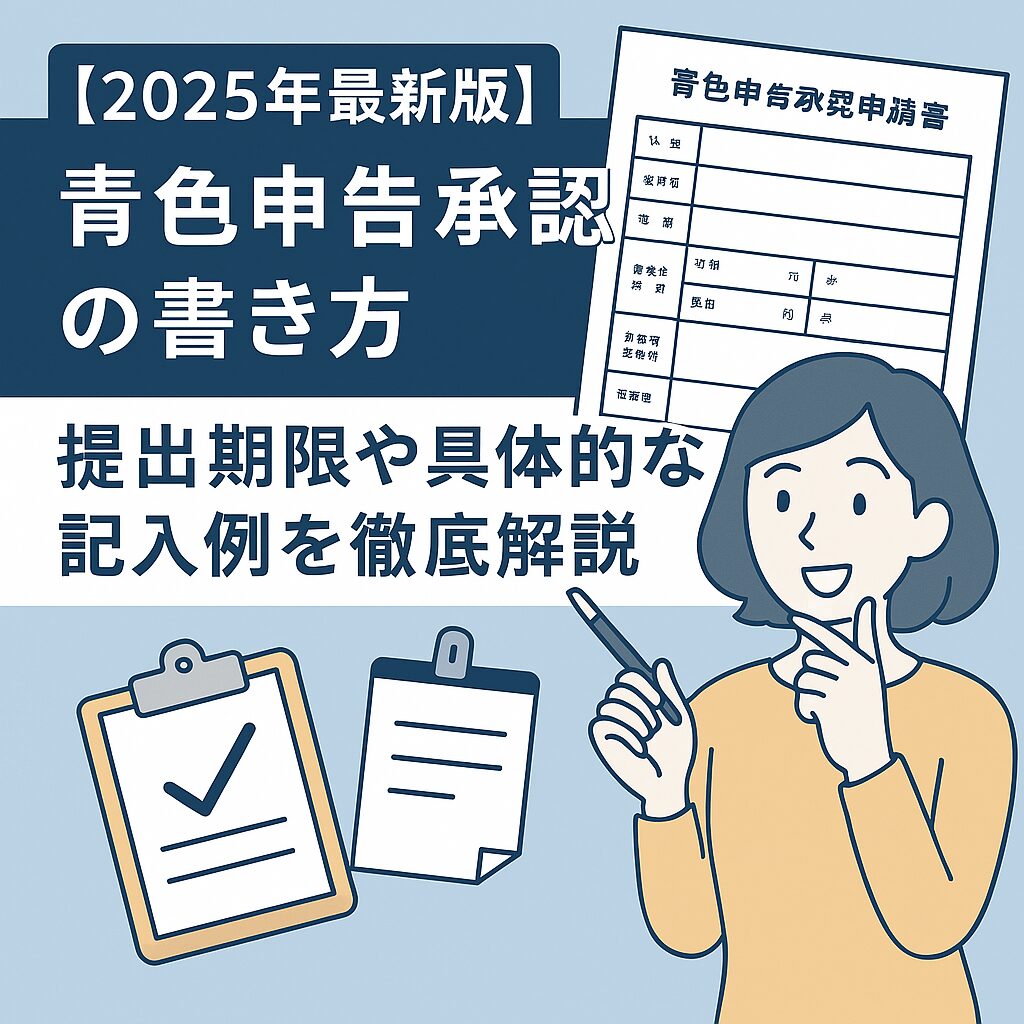「開業したけど、青色申告って何か手続きが必要なの?」 「青色申告の手続きって期限があるって聞いたけど…」
個人事業主やフリーランスとして活動を始めたとき、最初に頭を悩ませるのが確定申告の方法です。特に税金面で有利な「青色申告」を選びたいと考える方は多いでしょう。
しかし、青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この申請を忘れると自動的に白色申告になってしまい、最大65万円の控除が受けられなくなります。
この記事では、青色申告承認申請書とは何か、いつまでに提出すべきか、そして具体的な記入方法までを詳しく解説します。これから開業する方も、すでに事業を始めている方も、ぜひ参考にしてください。
青色申告承認申請書とは?基本を理解しよう
青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告をするために必要な手続きのための書類です。この申請書を提出することで、税務署から青色申告の承認を受けることができます。
青色申告には、最大65万円の控除(複式簿記の場合)や赤字の3年間繰越など、白色申告にはない大きなメリットがあります。しかし、これらの特典を受けるためには、必ず期限内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
この申請書を提出していない場合、自動的に白色申告での申告となりますので、特に注意が必要です。
対象となる人
青色申告承認申請書の提出対象となるのは、以下のような所得がある方です:
- 事業所得(自営業、フリーランス、個人事業主など)
- 不動産所得(アパート・マンションなどの賃貸収入)
- 山林所得(山林の伐採による収入)
基本的には、事業としてお金を稼いでいる人は対象になると考えてください。
具体的には、以下のような方々が該当します:
- フリーランスのエンジニア、デザイナー、ライター
- 個人事業主(飲食店、小売店、サービス業など)
- 賃貸物件のオーナー
- インターネットでの物販やアフィリエイト収入がある方
- 副業として事業収入がある会社員
提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は、事業の開始時期によって異なります。
| 事業開始時期 | 提出期限 |
|---|---|
| その年の1月1日~1月15日までに開業した場合 | 3月15日まで |
| その年の1月16日以降に開業した場合 | 事業開始から2か月以内 |
例えば:
- 2025年1月10日に開業した場合:2025年3月15日までに提出
- 2025年5月1日に開業した場合:2025年7月1日までに提出
提出期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなります。期限には十分注意してください。
また、すでに開業していて白色申告をしている方が青色申告に切り替える場合は、青色申告を行いたい年の前年の12月31日までに提出する必要があります。
青色申告承認申請書の記入例
ここからは、青色申告承認申請書の記入方法について、項目ごとに詳しく解説します。
納税地
「納税地」の欄には、基本的に自分の住所を記入します。これは開業届に記載した住所と同じものを書きます。税務署からの連絡が届く住所となるため、正確に記入してください。
上記以外の住所
この欄は、住所地以外に事業所を借りている場合にその住所を記入します。自宅で事業を行っている場合は、記入不要です。
氏名・生年月日・職業・屋号
- 「氏名」:戸籍上の氏名をフルネームで記入します
- 「生年月日」:西暦で記入します
- 「職業」:自分の業種(事業内容)を記入します。例えば「プログラマー」「WEBデザイナー」「飲食店経営」など
- 「屋号」:事業で使用している屋号(お店の名前など)を記入します。屋号は必須ではないので、無い場合は空欄で構いません
所得税の申告年度
ここには、青色申告を受けようとしている申告年度を記入します。例えば、2025年分の確定申告で青色申告を行いたい場合は「令和7年分」と記入します。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
この欄には、事業を行っている場所の名称と住所を記入します。
- 個人宅で事業している場合:自宅の名称(マンション名など)と住所
- 店舗で販売している場合:その店舗の名称と住所
- 不動産所得の場合:その不動産の名称と住所
例)
- 事業所や店舗の場合:「○○店」「○○本店・支店」など
- 不動産所得の場合:「○○コーポ」「○○荘」など
事業所や不動産が複数ある場合は、そのすべてを記載する必要があります。用紙に書ききれない場合は、別紙に記載して添付しましょう。
所得の種類
自分の事業の種類に当てはまるものにチェックを入れます。
- 事業所得:一般的な個人事業主、フリーランスの方
- 不動産所得:アパート・マンション経営などの賃貸収入がある方
- 山林所得:山林の伐採による収入がある方
今までに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめしたことの有無
以前に青色申告の承認を受けていた方は、状況に応じて該当する箇所にチェックを入れます。
- (1)「ある」:以前に青色申告の取り消しを受けたか、自ら取りやめた経験がある場合
- (2)「ない」:初めて青色申告を行う場合
初めて開業した方は(2)にチェックを入れます。
※過去に青色申告の承認の取り消しを受けたことがある場合、その取消の通知を受けた日から1年以上経過していないと再度青色申告の承認を受けることはできません。
本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
1月16日以降に事業を開始した場合、その事業開始年月日を記入します。開業届に記載した開業日と同じ日付を記入するのが一般的です。
相続による事業継承の有無
相続で事業を継いだ方は「ある」にチェックを入れ、「相続を受けた日」と「相続を受けた相手」を記入します。該当しない方は「ない」にチェックします。
簿記方式
青色申告には、複式簿記(65万円控除)と簡易簿記(10万円控除)の2種類があります。
- 「複式簿記」:青色申告65万円控除を受けようとしている人はこちらにチェック
- 「簡易簿記」:青色申告10万円控除を受ける場合はこちらにチェック
経理ソフトを使って複式簿記での記帳を行う予定であれば、複式簿記を選択しましょう。
備付帳簿名
青色申告で作成する帳簿にチェックを入れます。
- 65万円控除を受けようとする方は、最低限「現金出納帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」にチェックを入れ、他に作成する帳簿があれば追加でチェックします。
- 10万円控除の方は、「現金出納帳」「預金出納帳」にチェックを入れ、他に作成する帳簿があれば追加でチェックします。
関与税理士
確定申告を依頼している税理士がいる場合、その税理士の名前と事務所の住所を記入します。税理士に依頼していない場合は空欄で構いません。
青色申告承認申請書の入手方法
青色申告承認申請書は、以下の方法で入手できます。
1. 税務署で直接受け取る
最寄りの税務署で直接申請書を受け取り、手書きで記入する方法です。質問があればその場で相談することもできます。
2. 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページから申請書のPDFファイルをダウンロードできます。PDF上で入力することも、印刷してから手書きで記入することもできます。
国税庁ホームページ:所得税の青色申告承認申請手続
3. 【PR】会計ソフトやウェブサービスを利用する(おすすめ!)
会計ソフトやウェブサービスを利用すると、必要事項を入力するだけで申請書を作成できます。また、開業届など他の必要書類も併せて作成できるサービスもあり、初めての方も安心です。
特にマネーフォワードやfreeeなどの会計ソフトでは、青色申告に必要な複式簿記の記帳も自動化できるため、青色申告を検討している方におすすめです。
青色申告承認申請書の提出方法
作成した青色申告承認申請書は、以下の方法で提出できます。
- 税務署に直接持参する 管轄の税務署に直接持参します。受付印をもらえるので、確実に提出された証拠が残ります。
- 郵送で提出する 郵便で送る場合は、控えが必要なため2部用意し、1部に受付印を押してもらうよう返信用封筒(切手貼付)を同封しましょう。
- e-Tax(電子申告)で提出する e-Taxを利用すれば、オンラインで提出できます。マイナンバーカードが必要です。
開業に必要なその他の書類
青色申告承認申請書以外にも、開業時には以下の書類の提出が必要な場合があります。
- 開業届:事業開始から1ヶ月以内に提出が必要
- 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を支払う場合に必要
- 給与支払事務所等の開設届出書:従業員を雇う場合に必要
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員が10人未満の場合に便利
これらの書類も期限内に提出することが重要です。詳しい記入例は以下の関連記事をご覧ください。
まとめ:青色申告承認申請書の提出前チェックリスト
青色申告承認申請書を提出する前に、以下のポイントを確認しましょう。
- 提出期限を確認
- 1月15日までに開業:3月15日まで
- 1月16日以降に開業:事業開始から2か月以内
- 必要事項を漏れなく記入
- 納税地(住所)
- 氏名・生年月日・職業・屋号
- 所得の種類
- 簿記方式(65万円控除希望なら複式簿記)
- 備付帳簿名
- 提出方法を決定
- 持参、郵送、e-Taxのいずれか
青色申告は手続きが少し面倒に感じるかもしれませんが、最大65万円の控除など大きなメリットがあります。期限内に適切に申請を行い、税制上の特典を活用しましょう。
会計ソフトを利用すれば、青色申告に必要な複式簿記も簡単に対応できます。早めに準備を整えて、安心して事業に専念できる環境を作りましょう。
※この記事の内容は2025年4月現在の情報です。税制改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は税務署や国税庁のホームページでご確認ください。