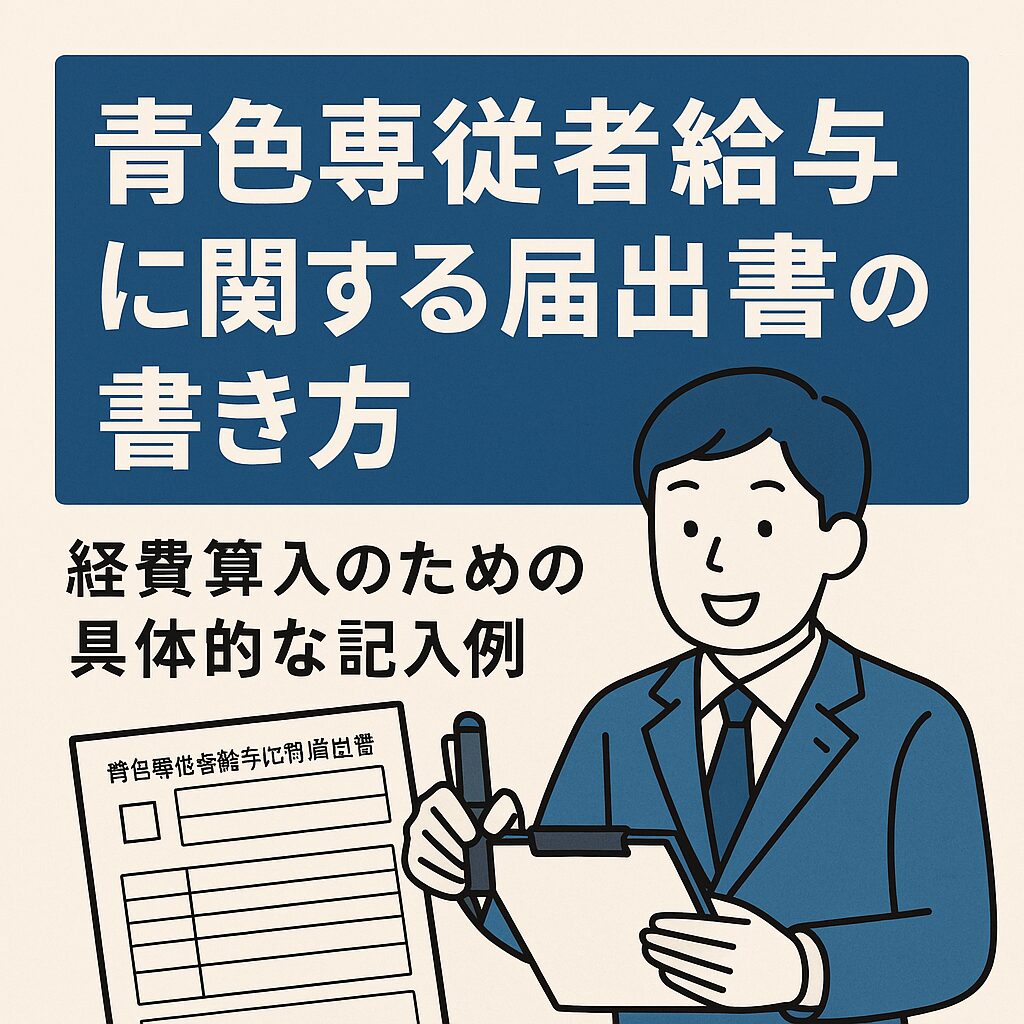「家族に手伝ってもらっているけど、給料を経費にできるって本当?」 「青色専従者給与の届出って何を書けばいいの?」
個人事業主やフリーランスとして活動していると、配偶者や家族に手伝ってもらうことも多いでしょう。そんなとき、青色申告をしていれば「青色専従者給与」として家族への給与を経費に算入できることをご存知ですか?
しかし、この制度を利用するには「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出しないと、たとえ配偶者や親族に給料を支払っても経費として認められません。
この記事では、青色専従者給与制度の基本から届出書の具体的な記入方法まで、わかりやすく解説します。家族の協力を正当に評価し、適切に税務処理するための必須知識を身につけましょう。
青色専従者給与とは?基本を理解しよう
青色専従者給与とは、青色申告者が事業に従事する配偶者や親族(青色専従者)に支払う給与を、一定の条件のもとで必要経費として認める制度です。
通常、個人事業主が家族に支払う給与は「家計の中でのお金の移動」とみなされ、経費として認められません。しかし、青色申告者には特典として、適正な給与であれば経費算入が認められるのです。
これにより、以下のようなメリットがあります:
- 家族への給与を経費として計上できる
- 所得分散による節税効果がある
- 家族の労働に対して正当な対価を支払える
ただし、この制度を利用するには、必ず「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
対象となる人
青色専従者給与に関する届出書の提出対象となるのは:
青色申告者で、配偶者や親族に給与を支払い、それを経費に算入したい人
重要なポイントとして、これは「青色申告者」のための特典です。白色申告者は、この制度を利用することができませんのでご注意ください。
また、専従者となる家族には以下の条件があります:
- 事業主と生計を一にしていること(同じ家計で生活している)
- 15歳以上であること(年齢制限あり)
- その年の12月31日現在で6か月以上専従していること
- 他の職業を主としていないこと(アルバイトなどは可能)
提出期限
青色専従者給与に関する届出書の提出期限は、事業の開始時期や専従者の就業時期によって異なります。
| 事業開始・専従者就業時期 | 提出期限 |
|---|---|
| その年の1月1日~1月15日に開業した場合、または新たに専従者がいることとなった場合 | 3月15日まで |
| その年の1月16日以降に開業した場合、または新たに専従者がいることとなった場合 | 開業または専従者就業の日から2か月以内 |
例えば:
- 2025年1月10日に開業し、配偶者を専従者とする場合:2025年3月15日まで
- 2025年5月1日に開業し、配偶者を専従者とする場合:2025年7月1日まで
- すでに開業していて、2025年6月1日から親族が専従者となる場合:2025年8月1日まで
提出期限を過ぎてしまうと、その年は青色専従者給与を経費として算入できなくなりますので、十分ご注意ください。
青色専従者給与に関する届出書の記入例
ここからは、青色専従者給与に関する届出書の記入方法について、項目ごとに詳しく解説します。
届出区分「届出」「変更届出」
まず、用紙の一番上にある「届出」「変更届出」のいずれかにチェックします。
- 初めて提出する場合:「届出」にチェック
- 既に届出をしていて内容(給与額など)を変更する場合:「変更届出」にチェック
納税地
「納税地」の欄には、基本的に自分の住所を記入します。これは開業届に記載した住所と同じものを書きます。
上記以外の住所
この欄は、住所地以外に事業所を借りている場合にその住所を記入します。自宅で事業を行っている場合は、記入不要です。
氏名・生年月日・職業・屋号
- 「氏名」:事業主の氏名を記入
- 「生年月日」:事業主の生年月日を記入
- 「職業」:事業主の業種(事業内容)を記入します(例:「Webデザイナー」「飲食店経営」など)
- 「屋号」:事業で使用している屋号を記入します。屋号は必須ではないので、無い場合は空欄で構いません
適用年月日
この欄には、この届出を適用させる年月日を記入します。専従者に給与の支払いを始める日付を記入します。
例えば、2025年4月から専従者に給与を支払う場合は「令和7年4月1日」と記入します。
専従者の氏名
専従者として給与を支払う家族の氏名を記入します。複数の専従者がいる場合は、それぞれ別の行に記入します。
続柄
事業主から見た専従者との関係を記入します。
例:
- 夫が事業主で妻が専従者の場合:「妻」
- 子が専従者の場合:「長男」「次男」「長女」など
経験年数
専従者がその仕事について持っている経験年数を記入します。
例えば、経理として3年間勤務していた配偶者が、あなたの事業の経理を担当する場合は「3年」と記入します。未経験の場合は「0年」または「なし」と記入します。
仕事の内容・従事の程度
専従者に担当してもらう仕事の内容と、どの程度働いてもらうかを具体的に記入します。
- 仕事の内容例:「経理事務」「営業事務」「店舗接客」「商品管理」など
- 従事の程度例:「平日9時~17時」「週5日・1日6時間程度」など
なるべく具体的に記入することで、実態に即した適正な給与であることを示せます。
資格等
専従者が持っている、担当業務に関連する資格があれば記入します。
例:「日商簿記2級」「宅地建物取引士」「調理師免許」など
資格がない場合は空欄で構いません。
給与の支給期
給与を支払う具体的な日にちを記入します。
例:「毎月25日」「毎月末日」など
給与の月額
専従者に支払う月額給与を記入します。
重要:ここで記入した金額が支給上限となります。実際の支払いがこの金額を超えると、超過分は経費として認められません。そのため、少し余裕を持った金額を記載しておくと良いでしょう。
金額を増やす場合は、変更届の提出が必要です。
賞与の支給期
賞与(ボーナス)を支給する場合、その時期を記入します。
例:「毎年6月・12月」「毎年7月・1月」など
賞与を支給しない場合は「なし」と記入するか、空欄でも構いません。
賞与の支給基準
賞与の具体的な金額や計算方法を記入します。
例:「給与の2か月分」「年間○○万円」など
こちらも記入した金額が上限となりますので、余裕を持った金額を記載しておくと良いでしょう。
昇給の基準
給与の昇給方針について記入します。
例:「毎年おおむね3%」「業績による」「能力・成果による」など
その他の参考事項
専従者が他にアルバイトをしている場合や学校に通っている場合など、参考となる情報を記入します。
例:「○○大学夜間部在学中」「週2日○○株式会社でアルバイト」など
特にない場合は空欄で構いません。
使用人の給与
専従者以外の従業員(使用人)を雇っている場合、専従者と同様の仕事をしている従業員の給与情報を記入します。
この欄は、専従者給与の金額が適正かどうかの参考になります。
例:「経理担当○○:月額○○万円、男性、経験5年」など
使用人がいない場合は、記入不要です。使用人がいても記入しなくても、青色専従者給与が認められなくなるわけではありません。
青色専従者給与に関する届出書の入手方法
青色専従者給与に関する届出書は、以下の方法で入手できます。
1. 税務署で直接受け取る
最寄りの税務署で直接申請書を受け取り、手書きで記入する方法です。質問があればその場で相談することもできます。
2. 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁のホームページから申請書のPDFファイルをダウンロードできます。印刷してから手書きで記入します。
国税庁ホームページ:所得税の青色申告承認申請手続
3. 【PR】会計ソフトやウェブサービスを利用する(おすすめ!)
会計ソフトやウェブサービスを利用すると、必要事項を入力するだけで申請書を作成できます。また、開業届など他の必要書類も併せて作成できるサービスもあり、初めての方も安心です。
特にマネーフォワードやfreeeなどの会計ソフトでは、青色申告に必要な書類作成や記帳も自動化できるため、青色申告を検討している方におすすめです。
青色専従者給与の要件と注意点
青色専従者給与を経費として認めてもらうためには、以下の点に注意しましょう。
1. 適正な金額であること
給与の金額は、専従者の業務内容や労働時間、能力に見合った「適正な金額」である必要があります。不当に高額な給与は、税務調査で否認される可能性があります。
一般的な目安としては:
- フルタイム(週40時間程度):月額15~30万円程度
- パートタイム(週20時間程度):月額7~15万円程度
2. 実際に給与を支払っていること
口座振込や現金での支払いなど、実際に給与を支払った証拠が必要です。帳簿上だけで処理せず、実際に支払いを行いましょう。
3. 届出書に記載した内容と実態が一致していること
届出書に「週5日・1日8時間勤務」と記載しておきながら、実際は「週1日・数時間」だけ働いているなど、実態が著しく異なる場合は、給与の経費算入が否認される可能性があります。
4. 青色専従者は他の職業を主としていないこと
青色専従者が他の会社に勤めながら、休日だけ事業を手伝うような場合、青色専従者として認められない可能性があります。アルバイトや副業程度であれば問題ありませんが、メインの仕事は事業主の事業を手伝うことである必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q1: 青色専従者給与の上限額はいくらですか?
A: 法律上の上限額は定められていませんが、「適正な金額」である必要があります。一般的には、専従者の業務内容・労働時間・スキルに見合った金額として、フルタイムで月15~30万円程度が目安となります。
Q2: 青色専従者に対して社会保険(健康保険・厚生年金)は必要ですか?
A: 個人事業主の場合、青色専従者は「家族従業員」の扱いとなり、原則として社会保険の適用対象外です。青色専従者は通常、事業主の国民健康保険や国民年金の扶養に入ります。ただし、法人成りした場合は社会保険の加入が必要になります。
Q3: 青色専従者給与を支払う場合、源泉徴収は必要ですか?
A: 青色専従者給与についても、一般の給与と同様に源泉徴収が必要です。
Q4: 青色専従者給与の届出をせずに給与を支払った場合はどうなりますか?
A: 届出をせずに給与を支払った場合、その給与は経費として認められません。また、給与として支払った金額は「家計への仕送り」とみなされ、所得税の計算上は事業主の所得となります。
Q5: 専従者は確定申告が必要ですか?
A: 青色専従者も給与所得者として確定申告が必要です。ただし、他に所得がなければ、年末調整で済ませることも可能です。
まとめ:青色専従者給与の届出前チェックリスト
青色専従者給与に関する届出書を提出する前に、以下のポイントを確認しましょう。
- 提出期限を確認
- 1月15日までに開業または専従者就業:3月15日まで
- 1月16日以降に開業または専従者就業:開業または就業から2か月以内
- 専従者の要件を確認
- 15歳以上である
- 事業主と生計を一にしている
- 年間を通じて6か月以上専従している予定
- 他の職業を主としていない
- 必要事項を漏れなく記入
- 納税地(住所)
- 氏名・専従者との続柄
- 給与の月額・支給日
- 仕事の内容・従事の程度
- 適正な給与額を設定
- 業務内容・労働時間・スキルに見合った金額
- 届出書記載の金額が上限となるため、余裕を持った設定
青色専従者給与制度を活用することで、家族の協力に対して正当な対価を支払いつつ、税務上のメリットも得ることができます。この記事を参考に、正しく届出を行い、制度のメリットを最大限に活用しましょう。
※この記事の内容は2025年4月現在の情報です。税制改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は税務署や国税庁のホームページでご確認ください。