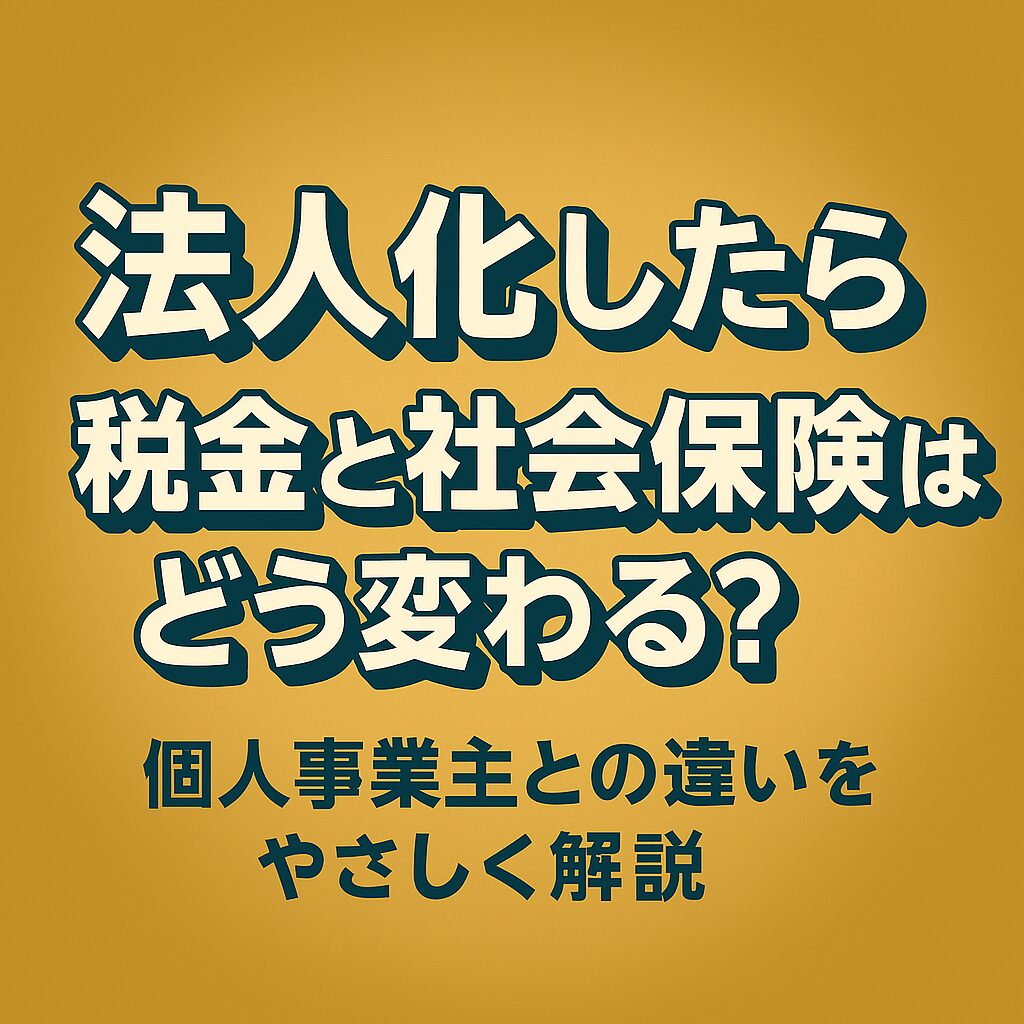「法人化したら節税できるって聞いたけど、本当に手取りは増えるの?」
「社会保険料は上がるの?下がるの?強制加入?」
「法人化するタイミングはいつがベスト?」
多くのフリーランスや個人事業主が抱えるこれらの疑問に、税理士監修のもと、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。この記事を読めば、法人化によるお金の流れの変化を理解し、あなたの状況に最適な選択ができるようになります。
法人化後に変わる「税金」の仕組み【図解】
法人化すると、税金の種類と計算方法が大きく変わります。シンプルに言えば「稼げば稼ぐほど法人化のメリットが出やすい」のが特徴です。
【個人事業と法人の税金比較】
【個人事業と法人の税金比較】
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 主な税金 | 所得税+住民税 | 法人税+法人住民税+法人事業税 |
| 税率の特徴 | 累進課税(稼ぐほど税率UP) | 基本定率(一定税率) |
| 税率(概算) | 所得195万円超〜:20%〜45% | 年800万円以下:15% 年800万円超:23.2% |
| 手取りが増えやすい | 年収300万円未満 | 年収300万円超 |
💡 なぜ法人は節税になりやすい?
個人事業主の場合、年収が増えると税率も45%まで上がりますが、法人の場合は基本23.2%(800万円までは15%)と低めの税率で安定しています。また、役員報酬として自分に給与を支払うことで、会社の利益を減らし、法人税の課税対象額を下げることができます。
役員報酬による節税メリット
法人化すると、あなたは「会社の代表者」となり、役員報酬という形で給与をもらう立場になります。
- ✅ 会社側のメリット: 役員報酬は会社の経費として計上できる
- ✅ 個人側のメリット: 給与所得控除(最低65万円)が適用される
- ✅ 設定の自由度: 報酬額は年間の収支見込みに応じて調整可能(ただし毎月同額が原則)
法人化で広がる経費計上の幅も重要なポイントです:
- 🔹 交際費: 個人事業より認められる範囲が広い(年800万円まで50%損金算入可)
- 🔹 福利厚生費: 社宅、慶弔費、健康診断など幅広く計上可能
- 🔹 退職金準備: 将来の退職金のための積立も可能
⚠️ 注意点
法人の場合、「会社のお金」と「自分のお金」を明確に区別する必要があります。私的流用と見なされると追徴課税のリスクがあります。
「社会保険」は強制加入に(原則)
法人化すると、社会保険の仕組みも大きく変わります。法律上、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
【個人事業と法人の社会保険比較】
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 加入する保険 | 国民健康保険+国民年金 | 健康保険+厚生年金 |
| 負担者 | 自分で全額負担 | 会社と個人で折半(会社負担分は経費) |
| 保険料の目安 (月収30万円の場合) | 国保:約3万円/月 国年:約1.6万円/月 | 健保:約3万円/月(半額負担) 厚年:約5.4万円/月(半額負担) |
| 保障内容 | 基本的な保障 | 充実した保障(傷病手当金など) |
社会保険のメリット・デメリット
メリット:
- 🟢 傷病手当金や出産手当金などの給付が充実
- 🟢 将来の年金受給額が増える可能性が高い
- 🟢 会社負担分(保険料の半額)が経費になる
デメリット:
- 🔴 保険料の総額が増える(特に厚生年金部分)
- 🔴 従業員を雇用する場合は必ず加入手続きが必要
「法人化すべきタイミング」の見極め方
「いつ法人化すべきか」は、あなたのービジネスの状況によって変わります。一般的な目安を紹介します:
法人化を検討すべき状況
- 年間の所得が500万円を超えている
- 取引先から「法人との契約希望」と言われた
- 従業員を雇用する予定がある
- 将来的に事業を拡大する計画がある
法人化を急がなくてもよい状況
- 収入が安定していない
- 年間の所得500万円未満
- 事務負担を増やしたくない
- まだビジネスモデルを模索中
【法人化の費用シミュレーション】
初期費用(法人設立時):
- 定款認証費用: 約5万円(電子定款なら印紙税4万円が不要)
- 登録免許税: 約15万円(資本金の0.7%、最低15万円)
- その他諸費用: 約3万円(印鑑作成、謄本取得など)
年間維持費用:
- 法人住民税(均等割): 約7万円(自治体により異なる)
- 税理士顧問料: 月3〜10万円(規模により異なる)
- 社会保険料(会社負担分): 給与の約15%
⇒ 法人化の費用対効果をプロに相談してみる:
「最低限かかる税金・コスト」も知っておこう
法人化すると、利益がなくても(赤字でも)必ずかかる固定費があります。この点は十分に理解しておきましょう。
🔸 赤字でも必要な法人特有の費用
- 法人住民税(均等割): 年間約7万円(自治体により異なる)
- 決算書類の作成義務: 法人は複式簿記による記帳と決算書作成が必須
- 税理士費用: 自分で全て対応するのは難しく、専門家に依頼するケースが多い
🔸 事務負担の増加
- 法定調書の作成・提出
- 消費税の中間申告・納付
- 月次での源泉所得税の納付
- 社会保険関連の事務手続き
⚠️ よくある失敗例
「とりあえず法人化しよう」という軽い気持ちで設立すると、思わぬコストや手間に驚くことがあります。特に年商1,000万円未満の場合は、個人事業主のままでも十分なケースが多いです。
法人化で活用できる「節税戦略」
法人化のメリットを最大限に活かすためには、いくつかの節税戦略が有効です。
1. 所得分散による節税
- 家族従業員への給与: 配偶者や家族を従業員として雇用し、所得を分散
- 複数役員の設置: 家族を取締役にして役員報酬を支払うことも可能
2. 福利厚生の活用
- 社宅費用の計上: 自宅の一部を社宅として会社が借り上げる形にできる場合も
- 各種保険の活用: 生命保険や医療保険を会社で加入することで経費に
3. 退職金制度の設計
- 将来の退職金: 役員退職金として受け取る際の税制優遇を活用
- 小規模企業共済: 掛金全額損金算入できる制度
よくある質問:法人化の「ギモン」解決
Q1: 法人化のタイミングはいつがベスト?
A: 一般的には年間の純利益が300万円前後を超えてきたタイミングが検討の目安です。ただし、事業の安定性や将来計画も考慮して判断しましょう。
Q2: 法人化するとどのくらい節税できる?
A: 例えば年間利益500万円の場合、個人事業主の税率(所得税+住民税)は約30%程度、法人税率は15%〜23.2%になります。役員報酬や各種控除を活用すれば、数十万円の節税効果が見込めるケースが多いです。
Q3: 法人化すると青色申告特別控除(65万円)はどうなる?
A: 法人には青色申告特別控除はありません。代わりに役員報酬に給与所得控除が適用されるなど、別の控除の仕組みがあります。
Q4: 法人の場合、いつでも好きな金額を引き出せる?
A: いいえ、「会社のお金」と「個人のお金」は明確に区別する必要があります。役員報酬は原則毎月同額とし、臨時的な引き出しは貸付金として処理するなど、適切な経理処理が必要です。
まとめ:「手取りが増える」のは条件次第
法人化によるお金の流れの変化をまとめると:
- 税金面
- 所得が増えるほど法人化のメリットが出やすい
- 経費計上の幅が広がる
- 役員報酬を活用した節税が可能
- 社会保険面
- 保険料の総額は増えるが、会社負担分は経費になる
- 保障内容が充実し、将来の年金額も増える可能性
- 事務負担・コスト面
- 固定費(法人住民税均等割など)が発生
- 税務申告や社会保険手続きなど事務負担が増加
- 税理士への依頼費用が発生する場合が多い
法人化は「誰にでもおすすめ」という単純なものではなく、あなたのビジネスの状況や将来計画によって判断すべき重要な決断です。
迷ったら、まずは専門家(税理士など)に相談し、あなたの事業に最適な選択を見つけましょう。「とりあえず法人化」ではなく、**目的と効果を明確にした「戦略的な法人化」**が成功への鍵です。