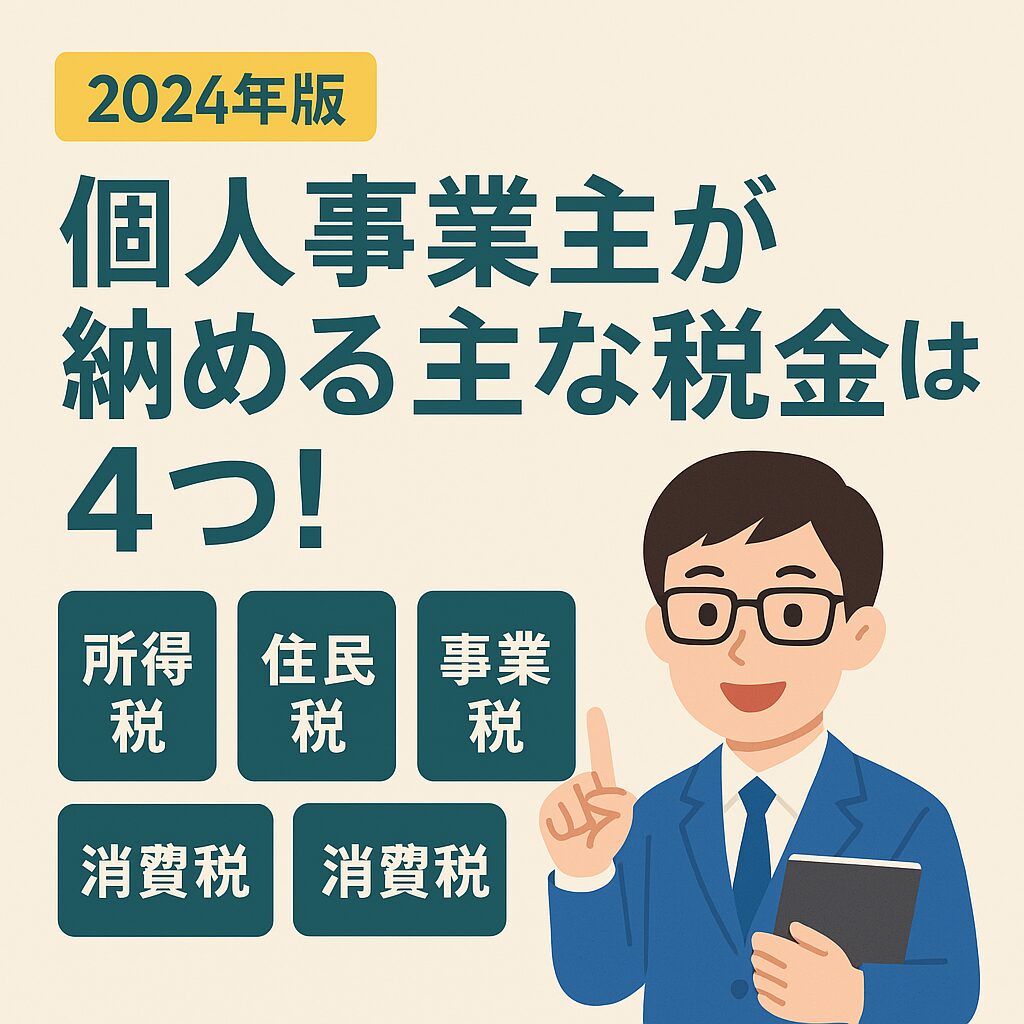「フリーランスになったけど、いつ、どんな税金を払えばいいの?」
個人事業主やフリーランスとして独立した多くの方が、税金の仕組みに戸惑います。特に開業初年度は、何の税金をいつ払うべきか、いくら準備しておくべきかが分からず不安になるものです。
本記事では、税理士監修のもと、個人事業主が納める4つの主要な税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税)について、それぞれの特徴から具体的な計算方法、納付時期までを徹底解説します。
この記事を読めば、税金の「いつ」「いくら」「どうやって」が明確になり、突然の高額請求に慌てることなく、計画的に事業運営ができるようになります。
個人事業主が納める4つの主要税金
個人事業主が主に納める税金は以下の4つです。それぞれ課税のタイミング、計算方法、納付先が異なるため、正確に理解しておくことが重要です。
| 税金名 | 納税先 | 納付時期 | 計算方法の特徴 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 税務署(国税) | 原則:翌年3月15日 | 累進課税、確定申告で自分で計算 |
| 住民税 | 市区町村(地方税) | 6月・8月・10月・1月 | 前年の所得に基づき通知が届く |
| 個人事業税 | 都道府県(地方税) | 8月・11月 | 所得から290万円控除後に税率3〜5% |
| 消費税 | 税務署(国税) | 翌年3月31日(原則) | 原則課税 or 簡易課税の選択可 |
これらの税金は、それぞれが別の制度で運用されており、すべて個別に納付する必要があります。次の章から、各税金の詳細と具体的な計算方法を解説していきます。
所得税:最も負担が大きくなりやすい税金 {#所得税}
所得税は、個人事業主の所得に対して国に納める税金です。利益が大きくなるほど税率が上がる**「累進課税」**が特徴で、多くの個人事業主にとって最も負担が大きい税金です。
所得税の税率(2025年時点)
所得税率は、課税所得額によって5%〜45%まで段階的に上がります。以下が2025年時点の税率表です。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算方法
所得税の計算は以下の流れで行います:
- 事業収入から経費を引き、事業所得を算出
- 事業所得から各種控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引き、課税所得を算出
- 課税所得に税率をかけ、控除額を差し引いて税額を計算
具体的な計算式は以下の通りです:
① 収入 - 経費 = 事業所得
② 事業所得 - 各種控除 = 課税所得
③ 課税所得 × 税率 - 控除額 = 所得税額
所得税の納付タイミングと方法
所得税は、原則として毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告し、納付します。ただし、事業規模によっては「予定納税」が必要になるケースもあります。
納付方法:
- 振替納税(口座引き落とし)
- クレジットカード納付
- e-Taxによるダイレクト納付
- 金融機関窓口・コンビニでの納付
💡 ポイント:青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられるため、所得税の負担を大きく減らせる可能性があります。開業時に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
住民税:前年の所得に応じて課税される地方税 {#住民税}
住民税は、あなたが住んでいる自治体(市区町村と都道府県)に納める地方税です。所得税と異なり、前年の所得に基づいて課税される点が特徴です。
住民税の仕組み
住民税は大きく分けて「均等割」と「所得割」の2つの要素で構成されています:
- 均等割:所得の多少に関わらず一律で課される税金(標準で年間5,000円程度)
- 所得割:前年の課税所得に対して約10%(市民税6%、道府県民税4%)の税率で計算
住民税の計算方法
住民税の基本的な計算式は以下の通りです:
①課税所得 × 10%(標準税率) - 税額控除 = 所得割額
②所得割額 + 均等割額 = 住民税額例えば、課税所得が300万円の場合、所得割は約30万円となります(自治体によって若干異なる場合があります)。
住民税の納付タイミングと方法
住民税は、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納付するのが一般的です。前年の所得に基づいて計算されるため、例えば2025年度の住民税は2024年の所得に基づいて算出されます。
納付方法:
- 普通徴収:納付書または口座振替で4回に分けて納付
- 特別徴収:給与所得者は毎月の給与から天引き(事業専従者給与を受け取る家族も対象)
💡 ポイント:開業初年度の翌年は「所得税の確定申告」と「前年の住民税の納付」が重なるため、資金繰りに注意が必要です。余裕を持った資金計画を立てましょう。
個人事業税:業種と所得額によって課税される地方税 {#個人事業税}
個人事業税は、事業を行う個人に対して都道府県が課す地方税です。すべての事業が対象ではなく、法定業種に該当し、かつ年間所得が290万円を超える場合に課税されます。
個人事業税の特徴と対象者
個人事業税の主な特徴は以下の通りです:
- 都道府県税(市区町村ではなく、都道府県に納める)
- 法定業種(70種類)に該当する事業のみ課税対象
- 所得から290万円の控除があり、それを超えた部分に課税
- 税率は業種によって異なる(3%〜5%)
個人事業税の税率と主な対象業種
| 区分 | 税率 | 主な対象業種 |
|---|---|---|
| 第1種 | 5% | 物品販売業、飲食店業、製造業、広告業、サービス業(一般的業種) |
| 第2種 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業など |
| 第3種 | 5%(または3%) | 医師、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、設計士、美容師など |
🔍 注意: デザイナー、コンサルタント、プログラマーといったフリーランスも個人事業税の対象です。一方、農業、林業、鉱物採掘、漁業、芸術家(作家・画家・音楽家)などは非課税業種となっています。
個人事業税の計算方法
個人事業税の計算式は以下の通りです:
(事業所得 - 各種控除 - 事業主控除290万円) × 税率(3%〜5%) = 個人事業税額例えば、サービス業で事業所得が500万円の場合:
(500万円 - 290万円) × 5% = 10.5万円個人事業税の納付タイミングと方法
個人事業税は、毎年8月(第1期)と11月(第2期)の2回に分けて納付します。都道府県から送付される納税通知書に基づいて納付します。
納付方法:
- 金融機関窓口・都道府県税事務所での納付
- 口座振替
- クレジットカード納付(自治体によって異なる)
- ペイジー(Pay-easy)対応のATM・インターネットバンキング
💡 ポイント:個人事業税は確定申告後に計算されるため、開業初年度は納税義務が発生せず、2年目の8月・11月から納付が始まります。計画的な資金準備を心がけましょう。
消費税:売上規模に応じて発生する間接税 {#消費税}
消費税は商品やサービスの消費に対してかかる間接税です。個人事業主の場合、売上規模が一定以上になると納税義務が発生します。
消費税の課税事業者判定
消費税の納税義務者(課税事業者)となるかどうかは、以下の基準で判断されます:
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
- 基準期間=前々年(個人事業主の場合は2年前の1月〜12月)
- 例:2025年の課税判定は2023年(前々年)の売上で判断
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
- 特定期間=前年の1月〜6月
- 例:2025年の課税判定は2024年(前年)1月〜6月の売上でも判断
- 事業者免税点制度の不適用
- 資本金1,000万円以上の法人は開業1年目から課税事業者
消費税の計算方法
消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります:
1. 原則課税方式
預かった消費税(売上にかかる消費税) - 支払った消費税(仕入にかかる消費税) = 納税額2. 簡易課税方式(課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能)
預かった消費税 ×(1 - みなし仕入率) = 納税額みなし仕入率は業種によって異なります:
| 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% |
| 第2種(小売業) | 80% |
| 第3種(製造業等) | 70% |
| 第4種(その他)<br>飲食業・サービス業など | 60% |
| 第5種(サービス業等)<br>運輸通信業・金融保険業など | 50% |
| 第6種(不動産業) | 40% |
👉 選択のポイント:仕入が少ない業種(コンサルタント、デザイナーなど)は簡易課税が有利になる場合が多いです。簡易課税を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
消費税の納付タイミングと方法
消費税は、個人事業主の場合、原則として翌年の3月31日までに申告・納付します。所得税の確定申告期限(3月15日)よりも少し遅いです。
納付方法:
- e-Taxによる電子納税
- 振替納税(口座引き落とし)
- クレジットカード納付
- 金融機関窓口での納付
💡 開業初年度の注意点:開業1年目と2年目は、原則として消費税の納税義務はありません(特定のケースを除く)。しかし、3年目以降の納税に備えて、売上から一定割合を積み立てておくことをおすすめします。
各税金の納付時期と方法一覧 {#納付時期と方法一覧}
個人事業主にとって、各税金の納付時期を理解しておくことは資金繰りの観点から非常に重要です。下記の年間スケジュールを参考に、計画的な資金準備を行いましょう。
年間納税カレンダー(2025年度の例)
| 時期 | 納付税金 | 対象期間 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 住民税(第4期) | 2024年分 | 納付書・口座振替 |
| 3月15日 | 所得税(確定申告) | 2024年分 | e-Tax・振替納税・窓口 |
| 3月31日 | 消費税 | 2024年分 | e-Tax・振替納税・窓口 |
| 6月 | 住民税(第1期) | 2025年分 | 納付書・口座振替 |
| 7月 | 所得税(予定納税第1期) | 2025年分 | 納付書・振替納税 |
| 8月 | 住民税(第2期) | 2025年分 | 納付書・口座振替 |
| 8月 | 個人事業税(第1期) | 2024年分 | 納付書・口座振替 |
| 10月 | 住民税(第3期) | 2025年分 | 納付書・口座振替 |
| 11月 | 個人事業税(第2期) | 2024年分 | 納付書・口座振替 |
| 11月 | 所得税(予定納税第2期) | 2025年分 | 納付書・振替納税 |
⚠️ 注意点:開業2年目(所得が発生した翌年)は特に税負担が集中しやすいため、十分な資金準備が必要です。所得税・消費税の確定申告と、前年分の住民税・事業税の納付が重なります。
確定申告の基本と納税額を抑える方法 {#確定申告と節税}
個人事業主にとって確定申告は、単に税金を納めるためだけでなく、適切な節税対策を行う重要な機会でもあります。
確定申告の基本
確定申告とは、1年間(1月〜12月)の所得と税額を計算し、翌年の2月16日〜3月15日に申告・納付する手続きです。
主な提出書類:
- 確定申告書A(事業所得用)または確定申告書B(複数所得用)
- 収支内訳書(白色申告)または青色申告決算書(青色申告)
- 各種控除証明書(医療費控除の明細書、社会保険料控除の証明書など)
納税額を抑える効果的な方法
- 青色申告を選択する
- 最大65万円の特別控除(e-Tax利用+複式簿記で記帳の場合)
- 30万円の特別控除(簡易帳簿で記帳の場合)
- 赤字の3年間繰越控除
- 経費を適切に計上する
- 事業に関係する支出はできるだけ経費として記録する
- 家事按分(事業と私用で共用する経費の区分)を適切に行う
- 減価償却資産(10万円以上の備品等)の管理を徹底する
- 各種控除を最大限活用する
- 社会保険料控除(国民健康保険料・国民年金保険料など)
- 小規模企業共済等掛金控除(掛金全額が所得控除の対象)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用(掛金全額が所得控除)
- 医療費控除(年間10万円または所得の5%を超える医療費)
💡 ポイント:節税対策は適法な範囲で行うことが重要です。不明点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問 {#よくある質問}
Q1: 開業初年度はどの税金を払えばいいですか?
A: 開業初年度に発生する主な税金は「所得税」です。事業所得が発生した場合、翌年3月15日までに確定申告を行い納付します。住民税は前年の所得に基づくため実質2年目から、個人事業税も確定申告後に計算されるため2年目(8月・11月)からの納付になります。消費税は原則として売上1,000万円超の事業者が対象で、条件を満たすと3年目から納税義務が発生します。
Q2: 売上が少ない場合でも確定申告は必要ですか?
A: 年間の所得金額が48万円(基礎控除額)以下の場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、次のケースでは売上が少なくても確定申告が必要です:
- 複数の収入源があり、給与所得以外の所得が20万円を超える場合
- 青色申告の承認を受けている場合(赤字でも申告が必要)
- 消費税の課税事業者に該当する場合
- 還付を受けたい控除(医療費控除など)がある場合
Q3: 税金はクレジットカードで支払えますか?
A: はい、国税(所得税・消費税など)はクレジットカードで納付可能です。国税庁の「国税クレジットカードお支払サイト」から手続きできます。ただし、決済手数料(税額に応じて変動)がかかります。地方税(住民税・個人事業税)も多くの自治体でクレジットカード納付に対応していますが、対応状況は自治体によって異なります。
Q4: 青色申告と白色申告はどちらを選ぶべきですか?
A: 基本的には青色申告をおすすめします。青色申告には以下のメリットがあります:
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 専従者給与を経費計上できる
- 30万円未満の減価償却資産を一括経費計上できる
ただし、青色申告は記帳の手間がかかるため、売上や経費が少ない場合や、開業直後で慣れない場合は白色申告でスタートし、事業が軌道に乗ったら青色申告に切り替えるという選択肢もあります。
まとめ:税金を正しく理解して計画的に準備しよう {#まとめ}
個人事業主が納める4つの主要な税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税)について解説してきました。各税金の特徴をまとめると:
| 税目 | 特徴 | 納付時期 | 計算のポイント |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 累進課税・確定申告が必要 | 翌年3月15日 | 青色申告で最大65万円の控除あり |
| 住民税 | 前年所得をもとに自治体が課税 | 6・8・10・1月(年4回) | 所得の約10%+均等割 |
| 事業税 | 所得290万円超かつ課税業種 | 8月・11月 | 290万円控除後に3〜5%課税 |
| 消費税 | 売上1,000万円超で納税義務 | 翌年3月31日 | 原則課税or簡易課税を選択可 |
おすすめツール|会計ソフトで確定申告をもっと簡単に!
税金の種類や計算方法を正しく理解しても、実際に申告・納付するとなると手間がかかります。そんな時に活用したいのが、クラウド型の会計ソフトです。
✅ 会計ソフトを使うメリット
- 自動仕訳&帳簿作成で日々の記帳が簡単に
- 確定申告書類も自動作成&電子申告対応
- 消費税や事業税にも対応、ミスを防げる
🎯 おすすめソフト
- マネーフォワード クラウド確定申告(PR)
- スマホからも使えて初心者にやさしい操作性
- 銀行・クレカ連携で自動記帳
- 青色申告・白色申告に完全対応
これからやるべきこと
- 会計ソフトを導入する
- 日々の記帳を効率化し、税金計算の手間を省く
- e-Taxとの連携で申告作業を簡略化
- 【PR】おすすめのクラウド会計ソフトはこちら
- 計画的な資金準備を行う
- 特に開業2年目は税負担が集中するため要注意
- 売上の20〜30%程度を税金の積立金として確保
- 専門家のサポートを検討する
- 複雑な税務は税理士に相談することで安心
- 税務調査対策としても有効
個人事業主としての成功は、ビジネスの力だけでなく、税金などの実務面をしっかり押さえることで実現します。この記事が、あなたのビジネスの成長と安定的な運営の一助となれば幸いです。
【関連記事】
- 個人事業主の確定申告ガイド|青色申告と白色申告の違いとは?
- 経費として認められるものの完全リスト|個人事業主・フリーランス向け
- 開業届と青色申告承認申請書の書き方・提出先まとめ
- フリーランスのための節税対策10選|適法に税負担を減らす方法
この記事は2025年4月現在の法令に基づいて作成しています。税制は改正される可能性がありますので、最新情報は国税庁または各自治体のウェブサイトでご確認ください。